目次
なぜ離婚は他人事ではないのか
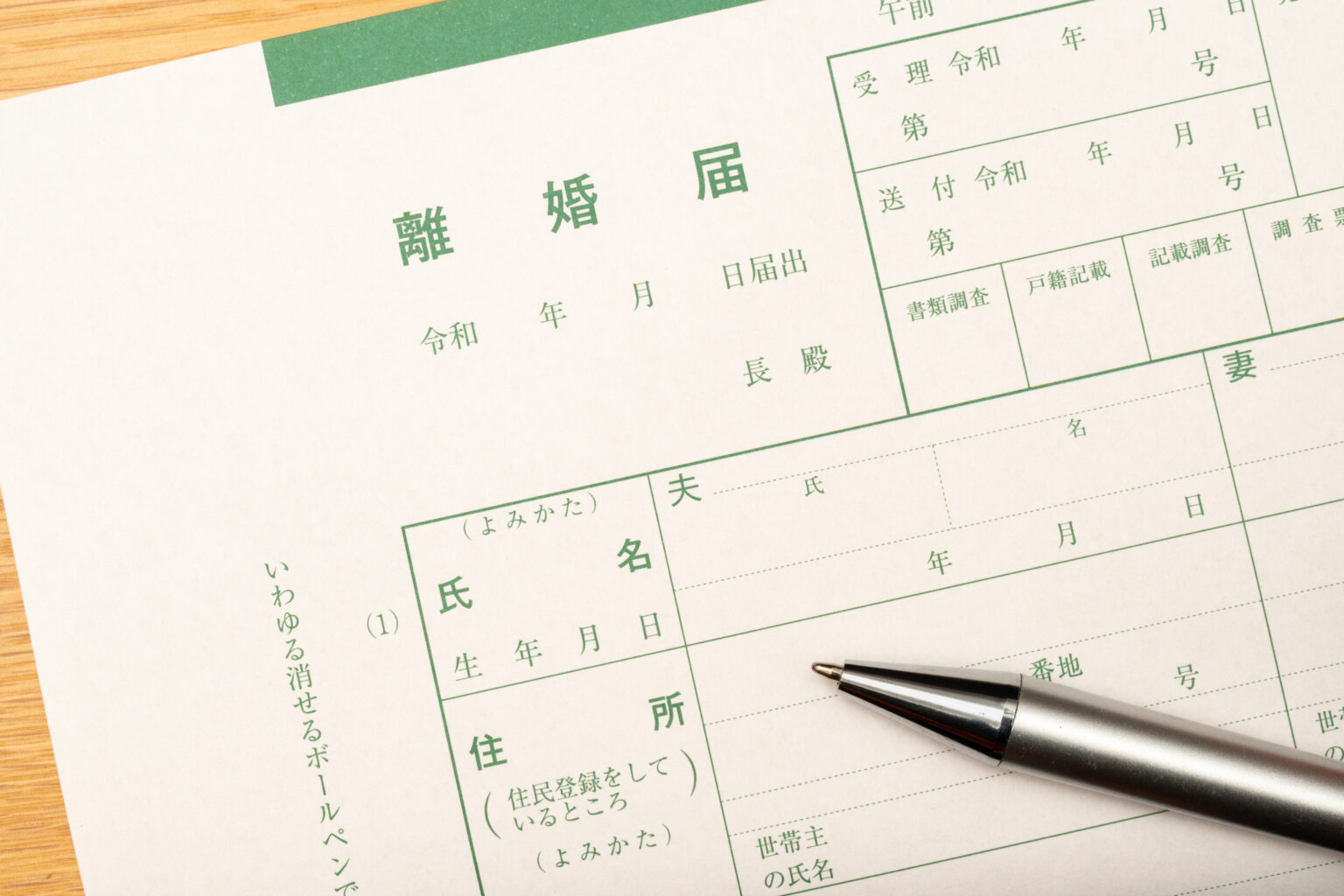
厚生労働省の調査では、2023年に日本で離婚した夫婦は18万組を超えています。これは結婚した夫婦の約3分の1に相当する数です。
新婚当初は「自分たちは離婚なんて考えられない」と思っていても、ちょっとしたすれ違いがきっかけで離婚することは珍しくありません。
離婚の原因を知っておけば、自分たちの夫婦関係を守りやすくなります。夫婦の絆を崩さないためにも、離婚につながる出来事を具体的に確認しましょう。
離婚のきっかけになる9つの出来事

離婚のきっかけは一つの大きな問題よりも、日常生活の小さな不満が積み重なって起こることがほとんどです。どんな理由で夫婦は別れを選ぶのか、その原因を見ていきましょう。
1. 性格や価値観が合わない
夫婦生活で一番多い離婚の理由は、性格や価値観の違いです。最初は違う部分に魅力を感じても、長く一緒に生活していると、その違いが我慢できなくなることがあります。
例えば、お金の使い方、趣味や休日の過ごし方、子どもの教育方針などで意見が合わないことが積み重なり、お互いに不満を抱えるようになります。話し合いがうまくいかず、次第に会話がなくなる夫婦も少なくありません。
2. 心を傷つける言葉や無視などの嫌がらせ
身体的な暴力だけでなく、言葉や態度による心への攻撃も離婚の大きな原因です。相手を馬鹿にする言葉、無視、冷たい態度は、相手の心を深く傷つけます。
これが毎日続くと、自分の価値がないと感じるようになり、心が離れてしまいます。直接暴力がないために気づかれにくいですが、離婚の大きな要因のひとつです。
3. パートナー以外との恋愛
他の異性との関係が発覚すると、夫婦の信頼関係は崩れてしまいます。たった一度の出来事でも、その後の関係修復が難しくなることがほとんどです。
一度失った信頼を取り戻すためには、多くの時間と努力が必要になります。相手への気持ちが冷めたり、家庭に居場所がなくなったと感じたりして、離婚に至ります。
4. お金に関するトラブル
お金の使い方や管理方法に問題があると、夫婦関係に亀裂が入ります。浪費癖があって生活費を入れない、借金を繰り返す、相手の収入をすべて自分が使ってしまうなどの経済的な問題は、相手の生活を追い込みます。
また、極端に節約を強いることも、不満を溜め込む原因になります。経済的な信頼を失うことは、夫婦生活を大きく揺るがします。
5. 親や親戚とのトラブル
結婚すると、お互いの家族とも関わりが生まれます。その中で、義理の親や親戚とうまくいかず、それが夫婦間のトラブルに発展することもあります。
義理の親の過干渉や、配偶者が義理の親の味方をしてしまうことで孤立感を覚え、ストレスが溜まってしまいます。相手が味方になってくれないことで、結婚生活を続けられないと感じてしまうこともあります。
6. 家事や子育てを一人に任せきりにする
家事や子育ての負担が一方に偏りすぎると、不満が積もり離婚の原因になります。
例えば、共働きにもかかわらず家事や子育てを片方がすべて担当している場合、負担が大きく精神的・肉体的な疲れから関係が悪化します。また、協力を求めても相手が無関心だったり、手伝いを拒否されたりすると、自分が尊重されていないと感じ、夫婦関係を続けることが難しくなります。
7. お酒やギャンブルへの依存
お酒やギャンブルにのめり込んでしまうと、家庭生活に大きな影響を与えます。依存している本人はもちろん、そのパートナーも精神的・経済的に苦しい状況に追い込まれます。こうした問題は「やめる」と口約束をしても簡単には改善できず、次第に家族が耐えきれなくなり離婚を決意するケースが多くなります。
8. 介護によるストレスや疲れ
夫婦どちらかの親が介護を必要とするとき、その負担が原因で離婚に至ることがあります。介護には肉体的な負担だけでなく、精神的、経済的な負担も伴います。
一人が介護をすべて負担し、それを当然と受け止められてしまうと、介護をしている側は心身ともに疲れ切ってしまいます。その結果、相手への不満や絶望感から離婚を考えるようになることもあります。
9. 子どもに対する不適切な態度
パートナーが子どもに暴力や暴言など不適切な行動を取った場合、夫婦の関係に大きな亀裂が入ります。子どもの安全や未来を守るために、離婚を選ぶことは珍しくありません。子どもを守る行動は、親として当然の責任でもあります。
結婚した頃のように仲良く暮らすための工夫

結婚したばかりの頃は、お互いの良いところが目に入り、小さなことでも嬉しく感じるものです。
しかし、時間とともにその気持ちを忘れてしまう夫婦は多くいます。夫婦がずっと仲良く暮らすためには、毎日の生活の中でお互いの存在を大切にする意識を持つことが大切です。
例えば、普段の会話で相手への感謝や労いを言葉にするだけでも、夫婦関係は大きく変わります。また、意見が食い違ったときも、相手を否定するのではなく、お互いの違いを受け入れた上で話し合う姿勢が重要です。家事や育児についても、分担を決めてお互いが無理なく協力できる環境を作ることが、お互いを尊重することにつながります。
小さな努力の積み重ねで、結婚当初のような仲の良い夫婦関係を築くことができます。
夫婦関係を改善するために試したいコミュニケーション方法
夫婦関係を改善するには、普段のコミュニケーションの質を高めることがポイントです。
たとえば、相手の話を最後までじっくり聞き、自分の意見を押し付けないように心がけましょう。また、夫婦で話すときはテレビやスマホを一旦やめて、しっかり相手の顔を見ながら話すことで、お互いの気持ちを理解しやすくなります。
夫婦で共通の楽しみや趣味を持つこともおすすめです。一緒に何かを楽しむ時間を増やせば、自然と会話が生まれ、気持ちの距離も縮まります。何気ない日常会話を積極的に楽しむ姿勢が、夫婦の絆を深めることにつながります。
まとめ
離婚を防ぐためには、お互いが自分自身の行動や言葉を振り返り、相手を尊重し合う姿勢が必要です。特にコミュニケーションを取るときに感情的にならず、冷静に相手の気持ちを考えることで、夫婦の間に生まれる小さな不満を解消できます。
また、二人で共有できる趣味や楽しみを持つことで、普段から自然な会話が生まれ、より良い関係を築く助けになります。夫婦生活に問題を感じたときこそ、初心に戻り、互いの存在を大切に思う気持ちを伝えることが、離婚を避ける鍵になるでしょう。











