目次
思春期は何歳から始まって何歳で終わる?
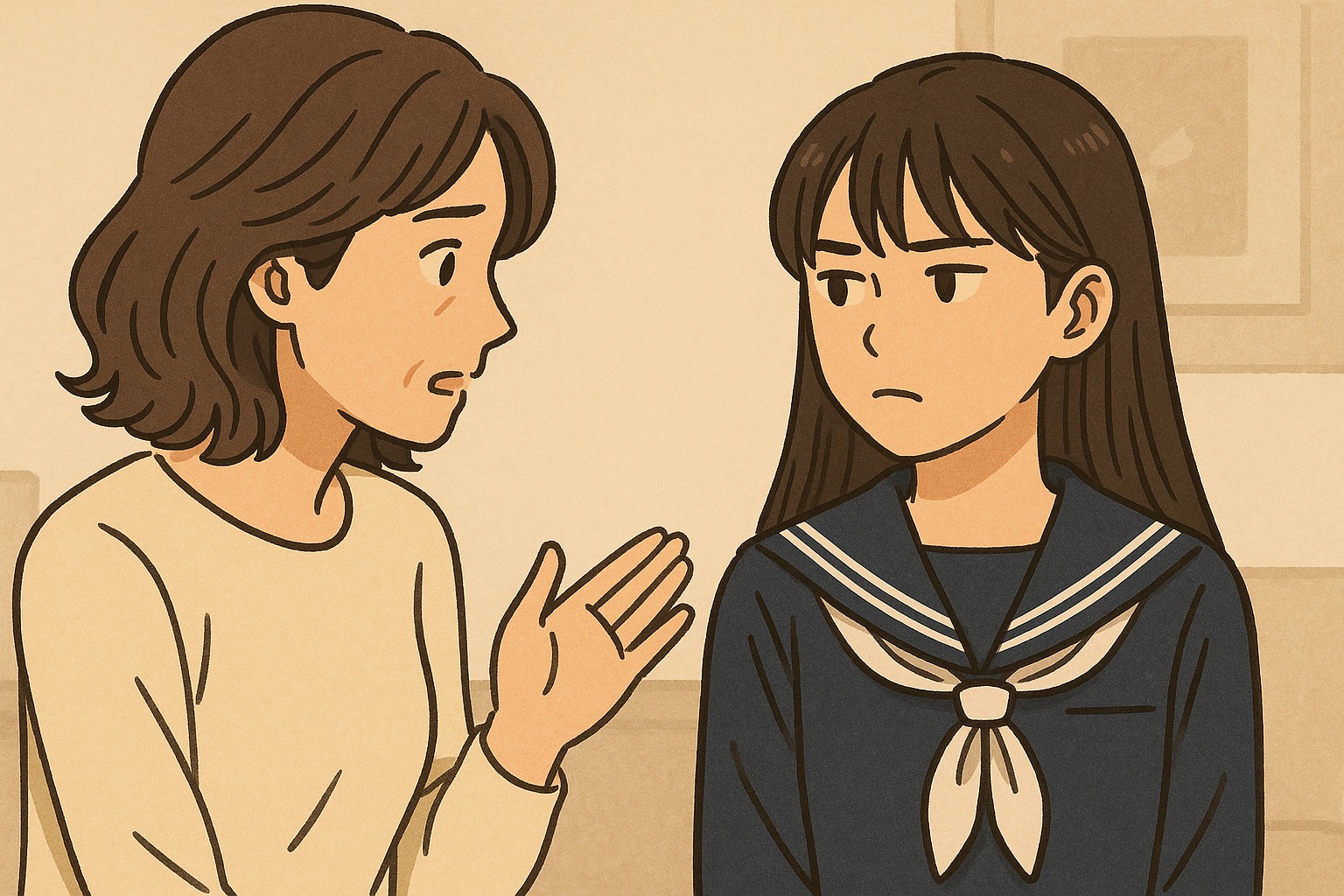
思春期は、子どもの身体と心が大きく成長する重要な時期です。一般的には、女子は8歳〜13歳ごろ、男子は9歳〜14歳ごろに始まり、17歳〜18歳ごろに終わるとされています。ただし、個人差が大きいため、この範囲から少しずれても異常ではありません。
この時期には「二次性徴」と呼ばれる身体の変化が現れます。二次性徴とは、身体が大人へと近づく過程で、性別ごとに異なる特徴が現れる現象です。
女子の身体の変化の順序
女子の場合、以下のような順序で身体の変化が進みます。
- 乳房の発育が始まる
- 陰毛が生える
- 身長が急激に伸びる
- 初経(初潮)を迎える
平均的には乳房が膨らみ始めてから2〜3年後に初経を迎えることが多く、初経の平均年齢は12歳前後とされています。
男子の身体の変化の順序
男子の場合、以下のような順序で変化が現れます。
- 精巣(睾丸)が大きくなり始める
- 陰毛が生える
- 身長が急激に伸びる
- 声変わりが起こる
男子は女子より約2年ほど遅れて思春期が始まることが多く、身長が伸びるピークの時期も女子に比べて遅めです。
思春期が始まるタイミングは、栄養状態や環境によって影響を受けることがあります。また、「うちの子は早すぎるかも?」「遅いのでは?」と不安になる親御さんもいますが、女子で8歳未満、男子で9歳未満に思春期の兆候が現れた場合、あるいは女子で15歳まで初経がない場合、男子で14歳まで精巣の変化がない場合は、小児科医に相談すると安心です。
思春期はなぜ大事な時期なの?

思春期には、身体だけでなく心にも大きな変化が起こります。自分が何者なのかというアイデンティティ(自己の存在)を考え始め、自立したいという欲求が強くなります。その一方で、心が不安定になりやすく、親や周囲の人間との関係に戸惑うことも多くなります。
この時期に親が子どもの気持ちを理解し、適切なサポートを行うことで、子どもは健全な自尊心を育て、自分らしく成長していくことができます。
思春期の子どもへの接し方で大切なこと

思春期の子どもは心も身体も不安定なため、親が接する際には細かな配慮が必要です。親の接し方によって、子どもの心の成長は大きく変わります。ここでは親が子どもに接する際に意識すべきことを解説します。
できたことは具体的に褒める
思春期の子どもは表面上そっけなく見えても、親からの肯定を強く求めています。子どもが何か良いことをしたときには、具体的に褒めるようにしましょう。
たとえば、「勉強頑張っているね」よりも、「昨日のテスト勉強、集中していたね」と具体的に伝えると、子どもにとって親から認められていると感じられます。
親から具体的に褒められることで、子どもは自信を持ち、自己肯定感が高まります。
子どものプライバシーを尊重する
思春期の子どもは、自分の時間や空間を強く求めます。勝手に子どもの部屋に入ったり、荷物を触ったりする行為は避けましょう。子どもの個人的な領域を尊重することで、親への信頼が深まり、安心して相談できる環境ができます。
特に以下の行動は控えるべきです。
- 日記やスマホを勝手に見る
- 部屋を無断で片付ける
- 友人との会話を詮索する
子どものプライバシーを守ることは、親子関係を良好に保つために非常に重要です。
子どもの話をしっかり聞く
親が子どもの話を途中でさえぎったり、否定したりすると、子どもは口を閉ざしてしまいます。思春期の子どもは、話したいときに自分のペースで話すことを望んでいます。
子どもが話してきたら、まずは最後まで話を聞き、そのあとで親の意見を伝えるようにしましょう。親が傾聴する姿勢を示すことで、子どもは安心し、困ったときに相談しやすくなります。
興味や関心を否定しない
思春期の子どもは新しい趣味や興味を持ち始めます。その趣味や興味が親の理解できないものであっても、頭ごなしに否定するのは避けるべきです。
否定する代わりに、子どもが何に興味を持っているのかを理解しようとする姿勢を示しましょう。一緒に調べたり、話題にしたりすることで、親子の会話が増え、関係が良好になります。
親が感情的にならない
思春期の子どもが反抗的な態度をとるのは、自立したい気持ちと不安が混ざり合っているためです。このときに親が感情的に叱ったり怒鳴ったりすると、親子関係はさらに悪化します。
親がまず冷静になり、子どもの言動を理解しようと努力しましょう。冷静な対応が、子どもの感情の揺れを落ち着かせ、問題解決につながります。
思春期の子どもにやってはいけない親の行動
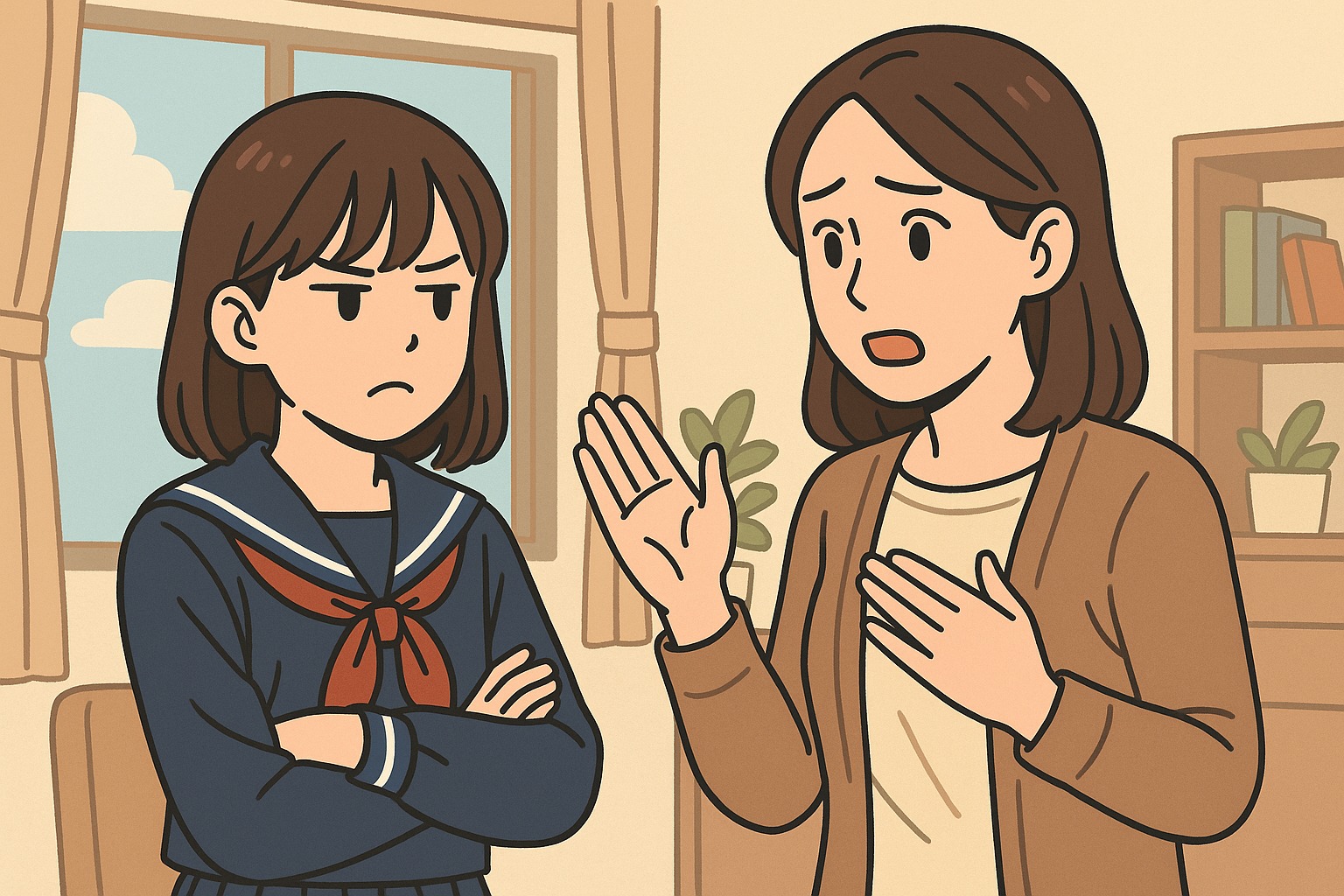
思春期の子どもと良い関係を築くためには、親として避けるべき行動があります。親は良かれと思ってやっていても、子どもに悪影響を与えることがあるため注意が必要です。
何でも否定する言葉を使う
思春期の子どもに対し、「全然ダメ」「あなたには無理」といった否定的な言葉を使うことは避けましょう。子どもは自己肯定感を失い、自信を無くしてしまいます。
否定的な言葉の代わりに、「こうするともっとよくなるよ」と前向きなアドバイスをしましょう。 子どもは自分の可能性を感じ、前向きな気持ちになります。
上から目線で話す
「こんなことも知らないの?」といった上から目線の態度は、子どもを傷つけることになります。思春期の子どもは自立心が強く、自分を一人前として見てほしいと考えています。子どもを一人の人間として尊重し、対等な目線で話しましょう。
感情的に怒鳴る・叱る
子どもが親の期待通りに動かないとき、つい感情的に怒鳴りたくなることもありますが、これは逆効果です。一時的に子どもを従わせることはできても、長期的には子どもの心に傷を与え、信頼関係が崩れてしまいます。
感情的にならず、落ち着いて理由を説明し、子ども自身が納得できるように諭すことが大切です。
子どもの暴言や問題行動を無視する
子どもが乱暴な言葉遣いや態度を示したときに放置するのはやめましょう。子どもは無視されることで、自分が見放されたと感じる可能性があります。また、問題行動がエスカレートする恐れもあります。
子どもが行き過ぎた言葉や態度を示したら、「その言い方は良くないよ」と冷静に伝え、社会的に好ましい行動を教えましょう。
他の子どもと比較する
「〇〇ちゃんはできるのに、なぜあなたはできないの?」と、他の子どもと比較するのは避けましょう。子どもは自己肯定感を失い、やる気をなくしてしまいます。子どもの良い部分を見つけて認め、個性を尊重することが重要です。
まとめ

思春期は単なる身体の成長期ではなく、子ども自身が自分の価値観を持ち、社会性を身につける重要な期間です。親が子どもの変化を深く理解し、適切な距離感を保つことで、子どもは健全な自立心を育むことができます。
親として大切なのは、「いつでも味方でいる」という安心感を与え続けることです。親自身も子どもと共に成長する気持ちを持つことで、親子の絆がより深まります。











