目次
早期離職が起こりやすい背景

厚生労働省の調査によると、新卒入社後3年以内に離職する人は大卒で33.8%、高卒では37.9%。この割合は過去10年ほぼ横ばいで、増えているわけではありません。
つまり、「すぐ辞める人が増えている」のではなく、昔から一定数いる構造的な現象なのです。
現代の働き方は「合わなければ変える」ことが当たり前になりました。転職市場の拡大や情報収集の容易さにより、我慢して働くよりも自分に合う環境を探す人が増えています。
ただし、早期離職の裏には、個人の性格や意志だけでは説明できない要素もあります。
たとえば、
- 採用時の情報が現場と違う
- 相談しづらい職場文化がある
- 評価や役割が曖昧で頑張りが見えにくい
こうした要因が重なり、「自分はこの職場でやっていけない」と感じやすくなるのです。
すぐに仕事を辞める人の9つの特徴

すぐに仕事を辞めてしまう人には、心理的・環境的な共通点があります。ここでは、その中でも特に共感を呼びやすい特徴を紹介します。
1. キャリアの軸が定まっていない
「この仕事で何を身につけたいのか」「どんなキャリアを築きたいのか」。この軸が定まっていない人は、仕事に対する動機が弱くなりがちです。
目の前の仕事に意味を見いだせないと、少しのつまずきで「この職場にいる意味がない」と感じてしまいます。入社の段階で“なんとなく”選んだ人ほど、その傾向は強くなります。
キャリアの方向性が曖昧だと、困難を乗り越える理由も曖昧になります。
努力を積み重ねても成果の実感が薄れ、モチベーションが続かないまま転職を繰り返してしまうこともあります。
2. 入社前のイメージと現実のギャップが大きい
「思っていた仕事と違った」。この言葉は、早期離職者の多くが口にします。
求人情報や面接で見えた“理想の姿”が、実際には別物だった――そんなミスマッチがきっかけです。
このギャップは、企業の情報開示不足だけでなく、求職者側が良い面だけを見てしまうことにも原因があります。
現場の雰囲気や実際の業務を知らないまま入社すると、初期のショックが大きくなり、「ここでは自分が成長できない」と感じてしまうのです。
本来なら、入社前に「大変な部分」も含めて説明を受けておくことが理想です。現実との落差を最小限にすることで、離職のリスクを減らせます。
3. 役割や評価の基準があいまい
どれだけ頑張っても評価されない――。そんな気持ちが積み重なると、人はやる気を失います。
何をすれば成果なのか、どこまで責任を持てばいいのかが曖昧な職場では、努力と結果の線が見えなくなります。
周囲と比較して「自分ばかり損をしている」と感じた瞬間、働く意欲は一気に低下します。
明確な評価基準と適切なフィードバックは、長く働くための支えです。
それがない環境では、自分の成長を実感できず、早期に退職を考える人が増えます。
4. 人間関係が築きにくく心理的安全性が低い
職場で「こんなことを聞いたら怒られるかも」と感じるような雰囲気があると、安心して働くことは難しくなります。
心理的安全性が低い環境では、失敗を共有したり相談したりすることができず、孤立しやすくなるのです。
次のような職場では注意が必要です。
- ミスを報告すると責められる
- 上司に相談しづらい
- チームの雰囲気が常に張りつめている
このような空気の中では、経験を積むよりも「早く逃げたい」という気持ちが強くなります。人間関係の悩みは、スキルや給与よりも深刻な離職要因になることが多いのです。
5. ストレスに弱く、感情的に判断してしまう
小さなミスや注意を過剰に気にしてしまうタイプの人は、ストレスが限界に達しやすい傾向があります。
感情が不安定な状態で退職を決めると、冷静な判断ができず、あとで後悔することもあります。
ただし、ストレス耐性は“個人の強さ”だけで決まるものではありません。
サポート体制が整っていない職場や、過度なプレッシャーを与える上司の存在など、環境要因も大きいのです。
一度立ち止まり、「何がストレスの原因か」を整理するだけでも、見え方は変わります。感情の波に流されないことが、キャリアを守る第一歩です。
6. 仕事にやりがいや成長を感じない
「このまま続けても、何も変わらない」――。そう感じた瞬間、仕事への意欲は急速に冷めていきます。
単調な業務や裁量の少なさは、特に成長意欲が強い人にとっては苦痛です。自分の努力が成果に反映されないと、仕事の意味を見失い、短期間で退職を考えやすくなります。
やりがいとは、単に楽しいという感覚ではなく、「成長できている」という手応え。
その実感がないと、心が動かなくなるのです。 自分の成長を可視化できる環境かどうかを意識することが、長く働くうえで欠かせません。
7. 完璧主義で自分に厳しすぎる
完璧を求めすぎる人ほど、自分を追い込んでしまいます。
小さなミスを許せず、「自分は向いていない」と早々に判断してしまうことも少なくありません。
完璧主義は一見“真面目で責任感がある”ように見えますが、長期的には心をすり減らします。100点を目指し続ける働き方は、どこかで限界を迎えるものです。
失敗を経験として捉える柔軟さを持つことで、仕事の継続力は大きく変わります。「できなかったこと」ではなく、「次にどう活かすか」に意識を向けることが重要です。
8. 職場に不公平感や不信感を抱きやすい
評価が偏っている、上司の態度に一貫性がない。そんな環境では「どうせ頑張っても報われない」と感じやすくなります。
不公平感は、仕事のモチベーションを静かに削っていきます。信頼できる上司や同僚がいない職場では、孤立感が強まり、辞める決断を後押しすることもあります。
不信を感じやすい職場には、次のような特徴があります。
- 成果よりも人間関係で評価が決まる
- 誰がどんな基準で判断しているのか不明
- 社内での情報共有が極端に少ない
信頼関係が築けない環境では、能力を発揮することも難しくなります。
9. 健康や価値観を守るために離れる
心身をすり減らしてまで働くべきではありません。過度な残業やハラスメントなどがある職場では、辞めることは逃げではなく、自己防衛のひとつです。
また、「会社の方針が自分の価値観と合わない」「倫理的に納得できない」場合も、早期に見切りをつけるのは健全な判断です。
仕事を続けることよりも、自分の健康や信念を守ることのほうが長期的には大切です。辞める決断を責める必要はありません。それは、心を守るための一歩でもあるのです。
「すぐ辞めるのは甘え?」という誤解と自己防衛
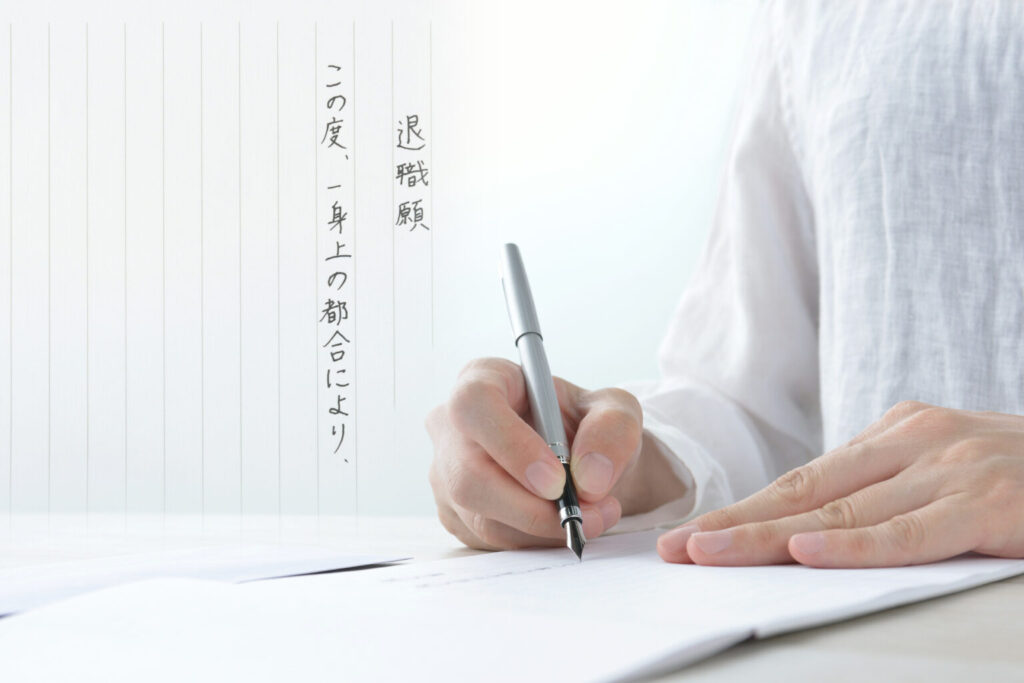
「根性が足りない」「我慢ができない」と言われがちな早期退職。しかし、それを単純に“甘え”と決めつけるのは危険です。
実際には、以下のような状況では「辞める」という判断が合理的なケースも多くあります。
- 長時間労働やハラスメントで健康を損なっている
- 不正や倫理的に疑問を感じる業務を強要されている
- 上司に相談しても改善が見込めない
これらは“逃げ”ではなく、自分を守るための選択です。誰にでも、限界を超えてまで耐える義務はありません。
一方で、感情的に辞めてしまうと、後悔につながることもあります。 「辞める」と「立て直す」そのどちらが自分を守る行動かを冷静に考えることが大切です。
社会は少しずつ、「早く辞める=悪いこと」という固定観念から離れつつあります。それでも、自分の中で迷いが生まれるのは自然なこと。
そのときこそ、自分を責めず、まずは立ち止まって状況を整理してみましょう。
仕事を辞めたくなった時のチェックポイント

「もう無理かもしれない」と思ったときこそ、感情で動く前に状況を整理することが大切です。
ここでは、退職を決断する前に確認しておきたいポイントを紹介します。
健康状態を確認する
体調不良や強い不安、睡眠不足が続いている場合は、心身が限界に近いサインです。仕事よりも健康を優先し、医療機関や専門相談窓口を利用することを検討しましょう。
職場環境を冷静に見つめ直す
人間関係や労働環境が一時的な問題なのか、それとも根本的に改善が見込めないのかを見極めます。改善の余地があるなら、異動や上司への相談で解決できる場合もあります。
評価や成長の機会があるか
努力が正当に評価されず、長期間成長を感じられない場合は、キャリア停滞のサインです。その職場に残る価値があるのか、慎重に考えましょう。
経済面の準備
退職後の生活資金や、次の職探しまでの期間を具体的に試算しておくことも重要です。焦りから妥協した転職をしてしまうと、同じ問題を繰り返す可能性があります。
自分の価値観とのズレ
「仕事が好きになれない」よりも、「自分の価値観と明らかに合わない」と感じるなら、無理に合わせる必要はありません。そのズレを無視すると、長期的には心が疲弊してしまいます。
これらの視点から考えると、辞めることが本当に“逃げ”なのか、それとも“再出発の準備”なのかが見えてきます。 辞めること自体は悪ではなく、自分の未来を整えるための選択なのです。
まとめ

早期離職には、本人の性格だけでなく、職場環境や社会構造といった複数の要因が重なっています。
「すぐ辞める人」と聞くとネガティブな印象を持つかもしれませんが、実際には自分を守るために必要な行動である場合もあります。
大切なのは、「辞める・辞めない」を白黒で判断することではなく、なぜそう思うのかを整理してから行動すること。
感情的な衝動ではなく、自分の健康・成長・価値観という3つの軸で考えると、後悔の少ない選択ができます。
そして何より、自分を責めないこと。
キャリアの道は一つではありません。早く辞めた経験も、次の一歩を見つけるための糧に変えることができます。











