目次
なぜ早食いをしてしまうのか

食事のスピードには個人差がありますが、周囲より圧倒的に早く食べ終えてしまう人もいます。食べるのが早い人には共通した心理や環境的背景が隠れていることが多く、それらは日常生活や性格にも密接に結びついています。
そのため、自分自身がなぜ早く食べてしまうのかを知ることで、健康的な食生活を送るためのきっかけになることがあります。
食べるのが早い人に共通する6つの特徴
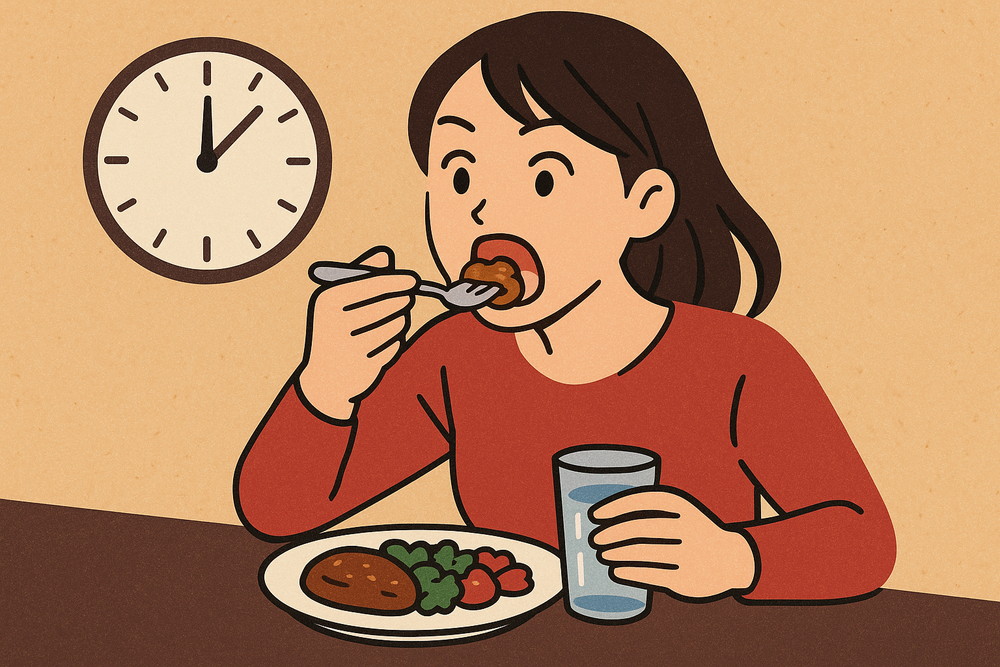
食べるのが早い人には、実はいくつかの共通する性格や心理的背景があります。それらの特徴を順番に見ていきましょう。
1. 時間にいつも追われている
食べるのが早い人は、多くの場合、日常生活で時間に追われています。仕事や学校、家事、育児、介護など、常に何かをしなければならない状況が続いているため、食事の時間もゆったりと取ることが難しいのです。
こうした状況では、食事が栄養を補給するだけの「タスク」になってしまい、味わって食べることを忘れてしまいます。特に職場や学校でのランチタイムは限られているため、自然と早食いになりがちです。
2. せっかちで落ち着きがない
もともと気が短く、待つことが苦手な人は食事も早く済ませてしまいます。食べるスピードが遅いと、それ自体にストレスを感じてしまい、早く次の行動に移りたいと思う心理が働きます。
このタイプの人は日常生活でも動作が速く、周囲がのんびりしているとイライラすることが多いです。早く食べることが効率的で良いことだと考えているため、食事のスピードを意識して遅くしようという気持ちになりにくい傾向があります。
3. 食べ物を味わうことに興味が薄い
食べ物に対する関心が低い人は、食事そのものを楽しむという感覚が少ないため、自然と食事の時間が短くなります。
美味しいものを味わって食べることよりも、空腹を満たすことに意識が向いてしまうため、噛む回数も少なくなり、流し込むように食べることが多くなります。食べることが楽しみではなく、単なる「作業」になってしまう人が多いのが特徴です。
4. 競争心が強く負けず嫌い
早食いになる背景には、強い競争心や負けず嫌いな性格も関係しています。兄弟姉妹が多かったり、食卓で早く食べなければ食べ物がなくなるという経験をした人ほど、食べる速度が速くなる傾向があります。
「早く食べないと負ける」という感覚が、大人になっても無意識に続いてしまい、周囲より先に食べ終えなければ気が済まないと感じる人もいます。
5. 衝動的で、我慢が苦手なタイプ
食べることに限らず、思いついたらすぐに行動に移してしまう衝動性が高い人や、ADHDのような特性を持つ人は、食べるスピードも速くなりやすい傾向があります。
これは、満腹感やゆっくり食べようという意識よりも先に、次のひと口を口に運んでしまうためです。我慢することが苦手なため、自分自身で食事のペースをコントロールすることが難しくなります。
6. 柔らかい食べ物を好む
食べるのが早い人は、咀嚼回数が少なくて済む柔らかい食べ物を選ぶ傾向があります。ハンバーグやパン、麺類など、噛まなくても飲み込みやすい食材ばかり食べていると、自然に咀嚼が少なくなり、食べるスピードが加速します。噛む回数が減ることで満腹感も遅れて感じるため、食べ過ぎにつながることもあります。
食べるのが早いことによるデメリット

食べるのが早いとさまざまな健康面や社会面でのデメリットが現れます。ここでは、早食いが引き起こす具体的な問題について詳しく見ていきましょう。
胃腸に負担がかかり、消化不良になる
早食いをする人は、食べ物を十分に噛まずに飲み込むため、胃や腸での消化がうまく行われません。
本来なら口の中で細かく噛み砕いてから飲み込むことで、胃や腸への負担を減らしています。しかし、早食いを続けることで消化不良を起こし、胃痛や腹痛、便秘や下痢などの消化器系トラブルに発展しやすくなります。
食べ過ぎによって太りやすくなる
食べるスピードが速いと、満腹感が得られる前に食べ過ぎてしまうため、肥満や体重増加のリスクが高まります。実際、日本の研究では、早食いをする人はゆっくり食べる人と比べて肥満になる確率が約2倍になるというデータもあります。太りやすい体質になれば、他の健康問題にもつながってしまいます。
血糖値が急激に上がり、糖尿病のリスクが高まる
食べ物を急いで飲み込むと、短時間で血糖値が一気に上昇しやすくなります。これを「血糖値スパイク」と呼びますが、繰り返し起こると糖尿病になる可能性が高くなります。
早食いは糖尿病の前段階である「インスリン抵抗性」を引き起こすリスクを高めるため、若い世代でも注意が必要です。
心臓病や血管の病気にかかる可能性が高まる
早食いの人は血液中の脂肪が増えやすく、動脈硬化など心臓や血管の病気につながる可能性があります。研究によれば、早食いをする習慣がある人は、ゆっくり食べる人に比べて約1.5倍も心臓病や動脈硬化のリスクが高くなると報告されています。
虫歯や口の中のトラブルが起きやすくなる
食べ物をよく噛まずに飲み込んでしまうと、唾液の量が減ります。唾液は口の中をきれいにして虫歯や歯周病を予防する働きがあるため、唾液が少なくなると虫歯や歯茎のトラブルが増えることになります。早食いを続けていると、口の中の健康状態が徐々に悪化する可能性があります。
周囲の人に悪い印象を与えやすい
早食いは見ている人に、がさつで落ち着きがない印象を与えることがあります。特にデートや会社の食事会、家族との食事などでは、早く食べ終えることで相手に焦りを感じさせることもあります。ゆっくり食事を楽しんでいる人に合わせられず、「マナーが悪い」と思われることもあるため注意が必要です。
早食いを治す方法

早食いは健康面やマナー面でさまざまなデメリットがありますが、意識して行動を変えれば改善可能です。ここからは、すぐに実践できる改善方法を紹介します。
食事の時に使う食器を小さくする
食べる量を自然に減らし、ゆっくり食べるようにするには、小さい食器を使うのが効果的です。特にスプーンやフォークを小さくすると、一口の量が減って食事のスピードを抑えることができます。
「一口30回」を目標によく噛んで食べる
噛む回数を意識的に増やすと満腹感を早めに感じられます。「一口につき30回噛む」を目標にすれば、自然と食べるペースが落ちます。また、よく噛むことで消化も助けられ、胃腸への負担も軽減できます。
噛み応えのある食材を意識して取り入れる
食事にきのこや根菜、こんにゃくなど、噛む回数が多くなるような食材を積極的に取り入れましょう。固めに調理したり、食材を大きめに切るだけでも自然に咀嚼回数が増え、食事時間が延びます。
食事の時間を15分以上確保する
最低でも15分以上かけて食事をするように心がけると、満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防げます。タイマーを利用して、自分がどれくらいの時間をかけているかを計測するのも効果的です。
食事に集中できる環境を作る
テレビやスマートフォンを見ながら食べるのをやめ、食事に集中しましょう。食べることに意識が向くことで、自然に食事のスピードが落ち、味わう感覚も取り戻せます。
ゆっくり食べることで得られるメリット

食べるのが早いと多くのデメリットがある一方、ゆっくり食べることでさまざまな良いことがあります。そのメリットを詳しく紹介します。
満腹感が早く訪れ、食べ過ぎを防げる
ゆっくり食べると、脳が満腹感を感じる時間を稼ぐことができ、食事量が自然と少なくなります。食べ過ぎを防ぐことで、肥満や生活習慣病を予防できます。また、一回の食事の満足度も高まり、無駄な間食が減る効果もあります。
消化がよくなり、胃腸の調子が整う
よく噛むことで唾液がしっかり分泌され、胃腸への負担を大きく減らすことができます。消化が良くなると胃もたれや腹痛が減り、便秘や下痢といった胃腸の不調も改善されやすくなります。
血糖値の上昇がゆるやかになり、糖尿病の予防になる
ゆっくり食べると、食後の血糖値が急激に上昇するのを防ぎます。血糖値の急な変動を抑えることで、糖尿病のリスクが減るだけでなく、食後に眠くなったり、集中力が低下することも少なくなります。
虫歯や歯周病になりにくくなる
よく噛んで食べることで、唾液がたくさん分泌されます。唾液には虫歯菌を洗い流し、口の中を清潔に保つ働きがあるため、虫歯や歯周病などのトラブルが起こりにくくなります。歯の健康を守るためにも、ゆっくり食べることが大切です。
脳が活性化し、集中力や記憶力が向上する
よく噛む行為は、脳への血液の流れを良くする効果があります。その結果、記憶力や集中力が高まり、勉強や仕事の効率もアップします。特に噛み応えのある食材を食べることで、脳の働きをさらに活発にできます。
味覚が鋭くなり、食事がもっと美味しく感じる
ゆっくりと食べ物を味わうことで、食材本来の味がよくわかるようになります。食事をゆっくり楽しむことで満足感が高まり、食べること自体が楽しく感じられるようになります。また、濃い味付けに頼らなくても美味しく感じるため、健康的な薄味の料理でも満足できるようになります。
まとめ
食べるスピードは習慣的なもので、無意識に早食いになってしまう人が多いのが現実です。しかし、ゆっくり食べることを習慣にすれば、心にも身体にも良い変化が現れます。特に、食事は人間にとって単なる栄養補給以上の意味を持っています。
食事の時間を意識的に楽しむことで、ストレスの軽減や心の豊かさにもつながります。今日から少しだけ時間をかけて、食事を「味わう時間」として楽しむように心がけてみてください。











