目次
そもそも「内祝い」とは何?

内祝いとは、本来は「内輪のお祝い」のことで、自分たちに起きた喜ばしい出来事を家族や近しい人にお裾分けする日本独自の習慣でした。昔はお祝いをいただく前に、自ら宴席を開いたり、お赤飯や紅白餅など縁起物を贈ったりして喜びを分かち合ったのです。
現代では、「お祝いをいただいたお返し」としての意味合いが強くなっています。内祝いを贈らないと「礼儀を知らない」と誤解される可能性もあるため、正しいマナーを知っておくことが大切です。
内祝いはいつまでに贈る?時期の目安と注意点
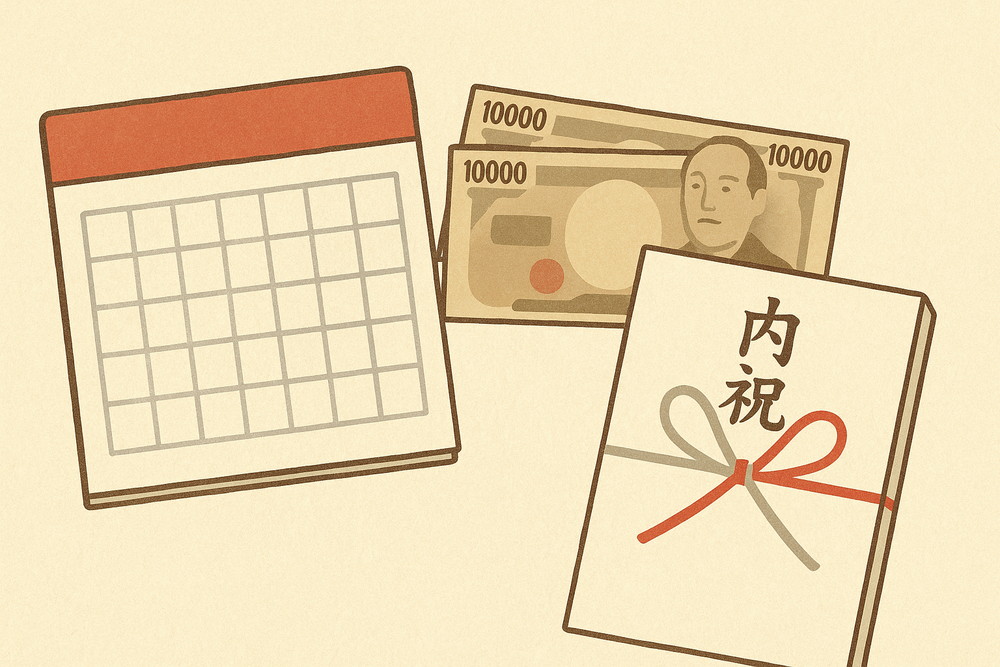
内祝いを贈るタイミングは、お祝いの種類ごとに目安があります。遅くなってしまった場合は、お詫びの言葉を添えて早めに手配しましょう。また、贈る相手が喪中の場合は、四十九日の忌明け後にするのがマナーです。
結婚内祝いの目安

結婚式に出席した方へのお返しは、当日の引き出物で済ませるのが一般的です。式に参加していない方からお祝いをいただいた場合は、1か月以内を目安に内祝いを贈ります。
出産内祝いの目安

出産祝いへのお返しは、赤ちゃんの生後1~2か月頃(お宮参り前後)に贈ることが一般的です。赤ちゃんの名前を入れた熨斗をつけて贈ると、名前のお披露目にもなります。
快気内祝いの目安

病気やけがでお見舞いをいただき、退院したけれど完治していない場合は「快気内祝い」を贈ります。時期は退院後10日〜1か月以内が目安です。完治した場合は「快気祝い」として贈りましょう。
内祝いの金額はどのくらい?相場と例外パターン

内祝いの金額は、もらったお祝いの半額程度(半返し)が基本とされています。ただし、高額なお祝いをいただいた場合や相手に気を使わせたくない場合は、3分の1程度の金額でも失礼にはなりません。大切なのは、金額よりも感謝の気持ちを伝えることです。
熨斗(のし)の書き方や水引のマナー

内祝いを贈る際には、「熨斗(のし)」をつけるのが正式なマナーです。熨斗には用途に応じて水引の種類が異なるため注意しましょう。
結婚内祝いの水引と表書き
結婚のお祝い事では「二度と繰り返さない」という意味を込めて、ほどけない「結び切り」の水引を使用します。熨斗の表書きは「内祝」または「寿」とし、夫婦の連名を記載します。
出産内祝い・新築内祝いの水引と表書き
出産や新築など、何度でも喜ばしいことには繰り返し結べる「蝶結び」の水引を選びます。表書きは「内祝」と記入します。特に出産内祝いの場合は、赤ちゃんの名前とふりがなを入れるのが一般的です。
快気内祝いの水引と表書き
快気内祝いでは、再び病気を繰り返さないという願いを込めて「結び切り」の水引を使用します。完治している場合は「快気祝」、通院など完治前であれば「快気内祝」と書き、本人の名前を記載します。
避けたほうがよい内祝いの品物とその理由

内祝いでは、相手に喜んでもらえる品物を選ぶのが大切です。ただし、縁起が悪いとされるものや、失礼にあたる品物もあるため注意しましょう。特に目上の方への贈り物は慎重な配慮が必要です。
避けたほうがよい代表的な品物は次のとおりです。
- 刃物(包丁やハサミ):縁や関係を「切る」ことを連想させるため。
- ハンカチ:「手切れ」を連想させるため。
- 靴下やスリッパなど足元で使う品物:目上の人を「踏みつける」というイメージを与えるため。
- 肌着や下着:目上の人に対して失礼とされるため。
- 日本茶や白いタオル:弔事でよく使われるため。
ただし、ガラス製品や陶磁器は、以前は「割れるから縁起が悪い」とされていましたが、最近では美しいデザインのものが贈り物として人気となっています。一律に避ける必要はありません。
内祝いを渡すときのマナーと心配り
内祝いは、贈る品物を用意するだけでなく、渡す際にも心配りが必要です。手渡しの場合は紙袋から品物を取り出して渡します。
配送で贈る場合は事前に到着日を相手に連絡し、荷物が届くことを知らせるのが丁寧なマナーです。また、品物だけでなく、感謝の気持ちを綴ったお礼状やメッセージカードを添えることで、より気持ちが伝わります。
まとめ

内祝いは形式やマナーだけではなく、自分自身の喜びや感謝の気持ちを表すための贈り物です。古来、日本人が大切にしてきた「人とのつながり」を再確認する機会でもあります。
高価な贈り物を無理に選ぶより、相手のライフスタイルや好みに合った品を選ぶことが、何よりも喜ばれるポイントです。また、相手に負担をかけないよう、品物のサイズや保存期間、使い道を考慮することも重要です。形式にとらわれ過ぎず、自分なりの心づかいを大切にしてください。











