目次
ネットの情報、鵜呑みにしていませんか…?

現代は、ネットやSNSにさまざまな情報が出回っています。どの情報をどの程度信じるかは、情報の受け取り手である人が選別しなければなりません。そのため、どのような情報でもすべて鵜呑みにしてしまうのは、非常に危険!
ネットの情報に騙されやすい人の特徴をまとめているので、家族で共有しつつ確認してみましょう。
『ネットの情報に騙されやすい人』の特徴5選

ネットの情報に騙されやすい人には、以下のような特徴があります。
1.発信している人の肩書を見て、情報を信じる
仕事などで肩書を持つ人は、多くいます。その中でも専門性が高く、幅広く世間に知られている肩書を持つ人の情報は、多くの人が信じやすいです。
権力ある職業を肩書にしている人の発信すべてが、真実というわけではありません。どのような肩書を持っていても、相手は自分と同じ人間なので、間違った認識をしていることもあればミスもします。また、肩書を利用した詐欺を働く人もいるので、肩書を見て情報を鵜呑みにするのが危険です。
2.情報の全体でなく、切り取った部分しか見ない
発信されている情報の中には、一部分だけを切り取って大げさに発信している人もいます。子どもの喧嘩を例に挙げると、叩かれて泣いている子が被害者だと思いやすいですよね。しかし、叩かれてしまうようなことを、相手の子に最初に仕掛けていたということもあります。
ネットの場合、顔が見えません。そのため、発信している情報の真実を100%引き出すことは不可能に近いです。そのことを加味せず、発信している情報をそのまま受け取ってしまうと、間違った認識を持ち続けることになります。
3.自分の興味ある分野の情報のみ目を通す
ネットやSNSは、基本的に自分の興味あるものだけに目を通す人が大半です。雑誌を購入する場合も、好きなものだけを購入して、好きな部分だけを読みますよね。しかし、ネットで好きな分野だけをあまりにも掘り下げてしまうと、ほかの意見を言う人を見たときに許せないという気持ちが湧きやすくなりので要注意!
常に広い視野を持つよう意識し、「こういう意見もあるんだな」と思える心のゆとりを持つことが重要です。
4.秘匿情報の公開など、特別感のある情報に飛びつく
ネットやSNSを見ていると、「私しか知らない情報」や「未公開の真実」などを発信している人もいます。そのすべてが嘘であるわけではないにしろ、鵜呑みにするのは危険です。リアルな人間関係でも、「ここだけの話」を聞くのが好きという人は特に注意しましょう。
5.情報を適切に処理できず、都合のいい情報だけ信じ込む
ネットやSNSには、毎日新しい情報が流れ込んできます。そのため、つい最近までの常識が偽りだったとひっくり返ることもあれば、否定派の人は手のひらを返したような意見を言っていることも、珍しくありません。
情報が多い分処理できなくなり、自分にとって都合のいい情報ばかりを信じ込んでしまうのはNG。視野が狭くなり、考え方が凝り固まる原因につながります。
嘘や間違いを見抜くために必要な考え方
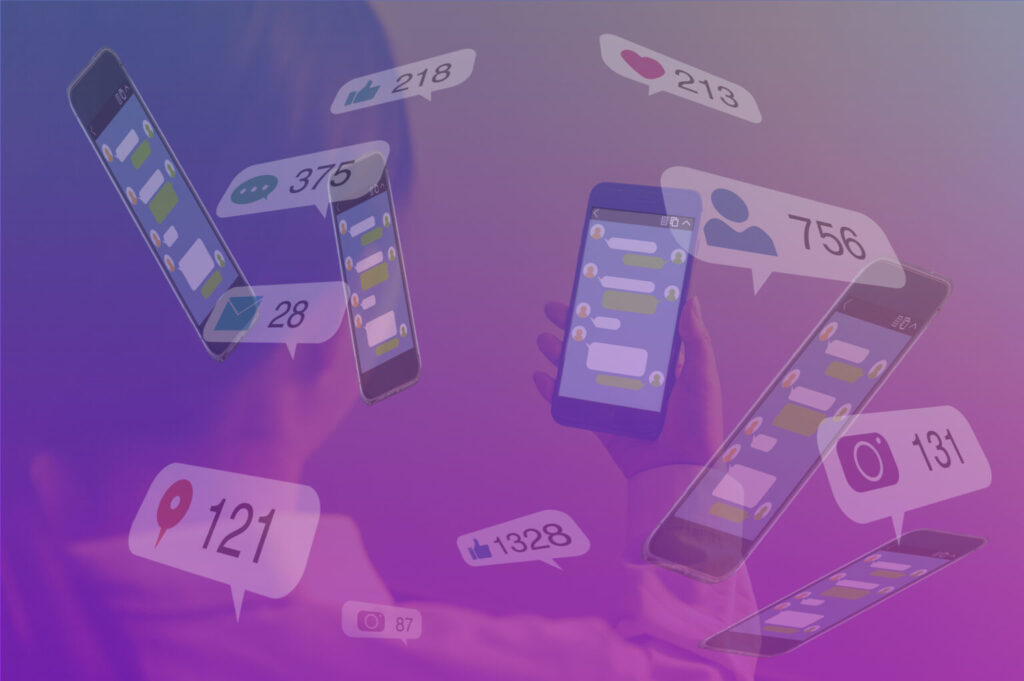
ネットにあまたある情報の嘘や間違いを見抜く方法は、以下の通りです。
- ひとつの事例について、複数の媒体の情報を確認する
- 耳障りがよく、過激な情報程、距離を置いて冷静に分析する
- 事態の全容を見ることができる媒体を確認する
全てを信じ込みすぎないという点を常に頭の片隅に入れておくと、情報を鵜呑みにせず冷静さを保ちやすくなります。
まとめ
ネットの情報は、真実もあれば嘘や偽りのものもあります。すべてを鵜呑みにせず、気になる情報があった場合は複数の媒体で検索をかけて情報を収集しましょう。











