目次
幸福度ってそもそも何?日本人の現状
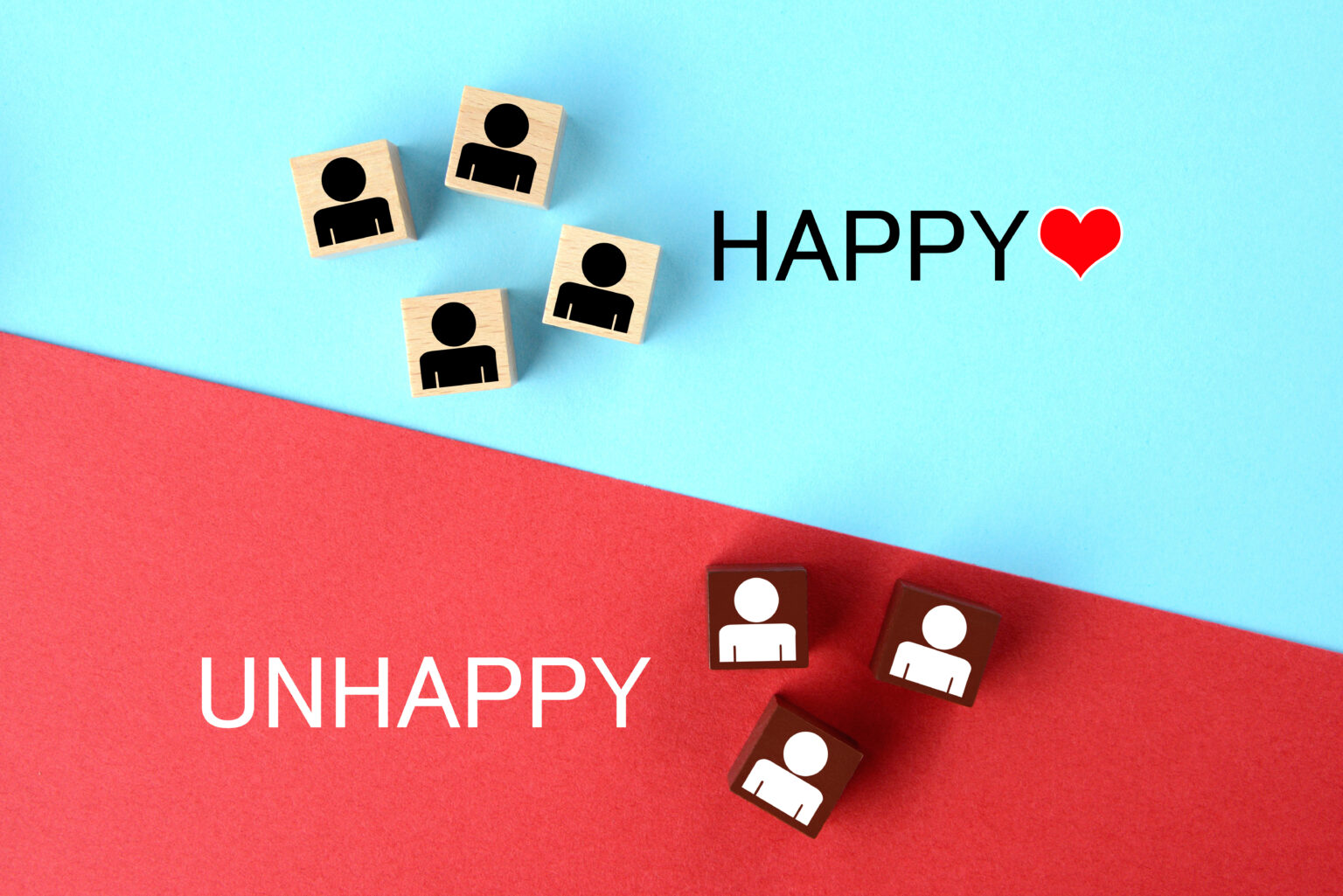
「幸福度」とは、人生にどのくらい満足しているか、どれほど幸せを感じているかを示す指標です。単なる満足感ではなく、日々の達成感や人とのつながり、人生の意味や目的を実感できているかといったウェルビーイング(心身の充足)の視点も含まれています。
幸福度はアンケートによる主観的な調査に加え、経済力、健康寿命、社会的なつながり、信頼感などを組み合わせて分析されるのが一般的です。
日本人の幸福度の現状
2025年の世界幸福度ランキングでは、日本は156カ国中55位と、先進国の中では低い位置にあります。イプソス幸福感調査2025でも「幸せ」と答えた日本人は57%にとどまり、30カ国中28位という結果でした。
幸福感が低い背景として、次のような傾向が見られます。
- 経済的な不安が大きい
- 将来に対する期待が極めて低い
- 人間関係にストレスを抱えやすい
- 社会的孤立を感じる人が多い
特に「現在の生活の満足度」と「将来の生活への期待感」が最下位水準にあることは深刻です。一方で、家族との関係や健康を幸福の源に挙げる人は多く、身近な人間関係が日本人の幸福感を支えていることも分かっています。
幸福度は変えられないものではありません。幸せになりたいなら、自分の幸福度を下げている行動を知り、少しでも改善することが必要です。これから、知らず知らずに幸福感を低下させている具体的な行動について説明していきます。
あなたの幸福度を下げる10のNG行動

私たちは無意識のうちに、幸福度を下げる行動をしていることがあります。その多くは習慣化されているため、自分では気づきにくいものです。以下では、特に共感を得やすいNG行動について詳しく見ていきます。
1. 他人と自分を比較する癖がある
SNSが普及した現代では、友人や見知らぬ他人の生活を簡単に覗き見ることができます。その結果、自分と他人を比較する機会が増え、「自分はあの人より劣っている」「あの人は楽しそうなのに私は違う」といったネガティブな感情を抱く人が増えています。
人間は本来、他人と比較して自分の位置を確認する生き物ですが、この比較が過度になると自尊心が傷つきます。さらに、「人と違う=悪い」という考え方が身についてしまい、自己肯定感を低下させる大きな要因となります。
2. 完璧を求めすぎる
仕事や家庭、人間関係などで完璧を目指すと、自分への要求が高くなります。完璧主義の人は小さなミスにも過剰に反応し、自分を責めたり、ストレスを抱えたりしやすいです。
完璧を追求すること自体は決して悪くありませんが、それが行き過ぎると、心の余裕がなくなり、結果として精神的な負担を増やします。さらに、自分だけでなく周囲にも同じ完璧さを求めるようになり、対人関係にも悪影響を及ぼすことがあります。
3. 多くの人と無理に付き合っている
多くの人と交流することは刺激を与え、視野を広げる効果があります。しかし、社交的でない人が無理をして多くの人と付き合おうとすると、疲れてしまいストレスがたまります。
人間には付き合える人数に限界があり、自分にとって居心地の悪い人間関係を維持しようとすると、精神的に消耗します。幸福度を維持するためには、広さより深さを重視し、心地よい人間関係を選んでいくことが大切です。
4. 周りの目を気にして本音を隠す
「人に嫌われたくない」「変に思われたくない」といった理由で、本当の自分を隠してしまう人は多いです。自分の意見や欲求を抑え続けると、本当の自分を見失ってしまい、幸福感が下がります。
心理学では、自分の内側の気持ちと外側の行動が一致していると、幸福を感じやすいと言われています。逆に、自分に嘘をつき続けると、自己嫌悪や漠然とした不安を引き起こし、人生の充実感が薄れます。
5. 週末に夜更かしをする
休日に夜更かしをして、翌日に寝坊をする生活は、短期的には解放感があります。しかし、長期的に見ると、体内時計が乱れて、心身の不調が出やすくなります。
この生活リズムの乱れは「社会的時差ボケ」と呼ばれ、疲労感、注意力の低下、イライラ感などの原因となります。幸福度を保つためには、週末も平日と同じリズムを維持することが重要です。
6. 自分の時間が多すぎて暇を持て余す
自由な時間は幸福にとって大切ですが、ありすぎるとかえって幸福度を下げることがあります。自由な時間が多すぎると、自分が何も生み出していない、無駄な時間を過ごしているという罪悪感を抱きやすくなります。
また、人間は目的を持ち、達成感を得ることで幸福を感じます。何もしないで過ごす時間が続くと、次第に人生の目的や充実感を感じられなくなり、精神的に不安定になりやすいのです。
7. 何でも自分一人で解決しようとする
人に頼るのが苦手で、何でも一人で抱え込んでしまう人は、ストレスを溜め込みやすくなります。誰にも相談せずに問題を解決しようとすると、行き詰まったときに孤独感や無力感を感じやすくなります。
私たちは他者と協力することで安心感や連帯感を得て、精神的に安定します。人を頼るという行為は弱さではなく、人間として自然な行動です。無理をせず、人に頼ったり相談したりする習慣を身につけることが重要です。
8. SNSに依存している
スマホでSNSを見るのが習慣化している人も多いでしょう。しかし、SNSで人の幸せな投稿を見続けると、無意識に自分と比較してしまい、嫉妬や自己嫌悪につながります。
SNSでの交流は一見つながりを感じさせますが、深い人間関係や信頼感を育てるのは難しく、孤独感を逆に高めることもあります。SNSの使用を適度にコントロールすることで、心の安定を保ち、幸福感を損なうのを防げます。
9. ネガティブな言葉をよく使う
「どうせ私には無理」「私はダメだ」といったネガティブな言葉を日常的に使っていると、自分自身を否定する意識が強まり、幸福感が下がります。
心理学では、言葉が感情や思考に影響を与えることがわかっています。ネガティブな言葉を繰り返し使うと、自分が実際にその言葉の通りになってしまう現象が起きます。できる限り自分に対して肯定的な言葉を使うように意識すると、精神状態が改善されます。
10. 新しいことを避ける
新しい挑戦を避けて、いつも同じことだけを繰り返すと、安心感はあるものの刺激がなくなり、人生が退屈になりがちです。変化や挑戦は脳を刺激し、達成感をもたらしてくれます。
小さな新しい体験でも幸福感は増します。普段行かないお店に行ったり、新しい趣味を始めたりするだけでも、日常に新鮮な喜びを感じることができます。
幸福度を高めるためにできる習慣

幸福度を下げる行動を理解したら、次は日々の生活で簡単に実践できる、幸福感を高めるための習慣を取り入れることが大切です。以下では、簡単に実践できる幸福度向上の習慣を紹介します。
小さなことに感謝する
人は幸せな出来事があってもすぐに慣れてしまい、幸福感が長続きしないことがあります。しかし、日常生活で起こる小さな出来事に感謝の気持ちを持つようにすると、毎日が豊かに感じられるようになります。
寝る前にその日にあった嬉しかったことを1つでもいいので思い出すようにしましょう。
短い時間でも運動する
運動をすると、ストレスが軽減され、幸福感を生むホルモンが分泌されることが科学的に証明されています。毎日10〜15分程度、軽い運動や散歩を取り入れるだけでも、気持ちが前向きになり、心身が健康になります。
自然の中で過ごす時間をつくる
自然の中で過ごす時間が多い人ほど幸福感が高いと言われています。週に120分程度、公園で過ごしたり、近所を散歩したりするだけでもストレスが軽減し、精神的な安定につながります。
人に親切なことをする
人に親切にすると、その行動をした本人も幸福感を感じることが分かっています。誰かのために簡単な手助けをしたり、身近な人に感謝の気持ちを伝えたりすることで、自分自身の幸福度も上げることができます。
十分な睡眠をとる
睡眠は心身の健康を維持するために欠かせません。毎日7〜9時間程度の十分な睡眠をとることで、脳が休まり、気分が安定します。睡眠不足が続くと、集中力や記憶力が低下するだけでなく、精神的なストレスが増え、幸福感も下がってしまいます。
まとめ

幸福度を下げる行動は、自分ではなかなか気づけないものです。そのため、時には自分自身の行動を振り返り、客観的に見る時間を持つことが必要になります。
幸福は自分の内面だけでなく、周囲の環境や状況にも大きく影響されるため、居心地の良い環境を作ることや、ストレスを感じる場所や状況を避ける工夫も必要です。
人生の幸福度を高めるには、自分自身を客観的に見つめ直し、無理のない範囲で生活を改善していくことが最も大切です。











