目次
喪主の役割とは?やるべきことを整理

喪主は、葬儀を取りまとめる中心人物です。葬儀を円滑に進めるために、事前に役割を知っておくと安心です。ここでは喪主が行うべき主な仕事を整理しました。
葬儀の準備と進行
葬儀の日程や会場、葬儀社との打ち合わせなどを喪主が中心になって行います。また、葬儀当日は式が順調に進むよう進行を確認し、トラブルがあればその場で判断を下します。
- 葬儀の日程や会場の決定
- 葬儀社との打ち合わせ、進行確認
- 式中の問題対応や判断
家族や知人への連絡・対応
故人の逝去を親族や関係者へ速やかに連絡します。葬儀の参列者対応、香典や供花の取りまとめも喪主の役割です。参列者の受付対応は他の家族や葬儀社スタッフに任せても問題ありません。
- 故人の訃報連絡
- 葬儀参列者への挨拶・対応
- 香典・供花の管理
宗教関係者への対応
故人が信仰していた宗教や寺院の関係者と連絡を取り、葬儀の進め方を相談します。お布施の金額や法要の手配なども喪主が行うのが一般的です。
- 宗教者への葬儀依頼と日程調整
- お布施の金額設定や支払い
葬儀後の手続きと管理
葬儀後にも喪主には多くの仕事があります。死亡届の提出や火葬許可証の取得、年金や保険の手続き、香典返しや法要の手配も喪主の役割となります。
- 死亡届と火葬許可証の申請(死亡後7日以内)
- 年金・保険など各種手続き
- 香典返しや法要の準備・実施
喪主はこれらの仕事を通して、葬儀が滞りなく行われるよう取り仕切ります。最近では葬儀社に多くの部分を任せられるため、すべてを一人で行う必要はありません。家族や葬儀社と協力して負担を分担しましょう。
喪主は誰が務める?優先順位と決め方

喪主を務めるのは「故人と最も縁の深い人」が一般的です。 配偶者や子どもが候補となりますが、家族で話し合って決定することが大切です。
喪主の優先順位と最近の傾向
法律上、喪主の決まりはありませんが、一般的な優先順位は以下の通りです。
- 配偶者(夫・妻)
- 子ども(長男・長女など)
- 親(父母)
- 兄弟姉妹
以前は長男が喪主を務めることが多かったですが、最近では性別に関係なく子どもが喪主を務めるケースが増えています。
喪主を決める際のポイント
喪主を決めるときには、次のポイントを考えて家族で相談しましょう。
- 故人が生前に希望した人がいるか(遺言や口頭)
- 候補者の体力や精神的負担に問題はないか
- 経済的な負担を引き受けられるか
- 家族内での関係が円滑に進むか
これらを踏まえて、家族内で無理なく喪主を決めましょう。喪主は必ずしも一人で務める必要はなく、家族の状況に応じて「共同喪主」として複数人で務めることもできます。
娘しかいない場合の喪主の決め方

娘しかいない場合、長女が喪主を務めることが一般的です。 しかし、必ずしも長女でなければならないわけではありません。家族内で相談し、適切な人を選ぶことが大切です。
娘が複数いるときは長女が優先される?
娘が複数いる場合、一般的には長女が第一候補になります。 ただし、次のような理由で長女が務めることが難しい場合もあります。
- 長女が遠方に住んでいてすぐに対応できない
- 体調や精神面で不安がある
- 経済的な負担が難しい
このような場合、次女以降の姉妹が務めても問題ありません。最近では、家族間の話し合いを尊重し、柔軟に決定する傾向があります。
娘婿が喪主を務めることも可能
娘が結婚している場合、娘婿が喪主を務めるケースもよくあります。 特に、娘が仕事や家庭の事情で多忙な場合、娘婿が代理で務めるとスムーズに進むことも多いです。
ただし、この場合も必ず家族の話し合いと合意を経て決定することが重要です。娘婿が務める場合、親族や参列者が違和感を持たないように、挨拶や説明の準備をしておくと良いでしょう。
親族がいない場合や頼れない場合の喪主の決め方
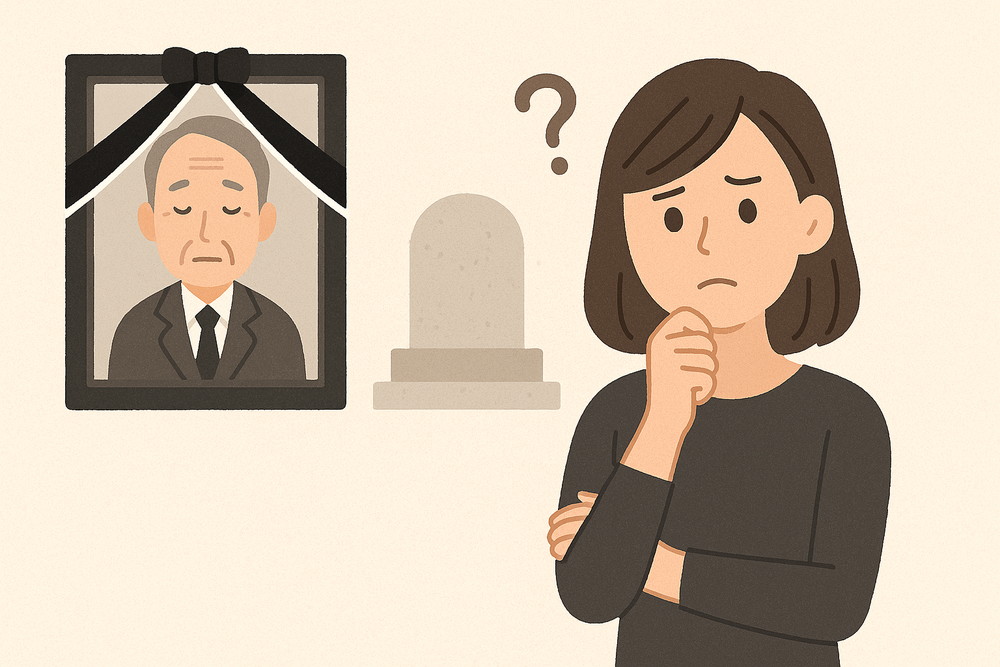
親族がいない、あるいは親族と疎遠で喪主を頼めない場合でも、葬儀は問題なく行えます。 以下のような方法で喪主を決めたり、葬儀を進めることができます。
友人や知人が喪主を務める場合
親族がいない場合、故人の友人や知人が喪主を務めることがあります。これは、近年特に増えてきたケースです。
ただし、友人や知人に負担をかけすぎないためにも、役割を限定し、葬儀社と協力して進めることが望ましいです。喪主を引き受ける側も、精神的・金銭的負担をよく考えて判断することが大切です。
後見人や宗教関係者に依頼する場合
身寄りがなく、誰にも迷惑をかけたくないという人の場合、普段お世話になっている宗教関係者や弁護士・行政書士などの後見人に喪主を依頼することも可能です。
この場合、葬儀社に相談すれば適切な人を紹介してもらえます。ただし費用がかかることもあるので、事前にしっかりと費用や役割について確認しましょう。
喪主代行サービスを利用する方法
最近では、喪主代行サービスを利用する人も増えています。 特に一人暮らしの高齢者など、頼れる親族がいない場合に便利です。主なサービス内容は次の通りです。
- 葬儀社との打ち合わせや日程調整
- 当日の挨拶や参列者対応
- 葬儀後の手続き代行
料金やサービス内容は提供会社によって異なるため、複数社を比較して検討しましょう。
喪主の負担を減らす方法

喪主には多くの負担が伴いますが、負担を分散・軽減する方法があります。 一人で全てを背負わず、周囲の協力やサービスを上手く活用しましょう。
共同喪主や施主と分担する
最近増えている方法が、複数人で喪主を務める「共同喪主」です。例えば、高齢の配偶者が葬儀の挨拶を行い、子どもが葬儀費用や準備を担当する、といった分担が可能です。
また、費用を負担する人を「施主」として喪主と分けることも可能で、これにより負担感が大きく軽減されます。
葬儀社に任せられることは任せる
喪主が全ての手続きを行う必要はなく、多くの場合、葬儀社に任せられる部分が多くあります。葬儀社が代行できる主な項目は以下の通りです。
- 死亡届や火葬許可証など役所への提出書類
- 宗教関係者への連絡や日程調整
- 香典返しの手配と発送
これらを葬儀社に任せることで、精神的・時間的な負担を大幅に減らせます。
まとめ
葬儀を円滑に進めるには、喪主の役割を理解し、家族や関係者で協力することが重要です。近年は家族構成や社会状況が変化し、柔軟な決定や分担が可能になりました。葬儀の在り方も多様化し、特に都市部ではオンライン葬儀や直葬(火葬式)など簡略化された形式が増えています。自分や家族の負担が少なく、故人を十分に偲べる葬儀を目指し、形式にとらわれず適切な方法を選びましょう。











