目次
拡大するSNS依存症の現状とリスク

近年、SNSの利用増加に伴い、その依存症が大きな問題になっています。SNS依存症とは、日常生活よりSNSを優先してしまい、利用時間や頻度を自分で制御できなくなる状態を指します。
日本国内のSNS利用者は2024年末時点で約8,452万人に達し、ネット利用者の79%を占めています。特にスマホ普及が進み、小学生や未就学児の使用も一般化したことで、問題の低年齢化が深刻です。
SNS依存症になると、感情や時間のコントロールが困難になり、睡眠不足や集中力低下など心身の健康にも悪影響を及ぼします。特に自己管理力が未熟な未成年に対しては、家庭や学校での早期の対策が必要です。
SNS依存症の典型的な5つの特徴とは?
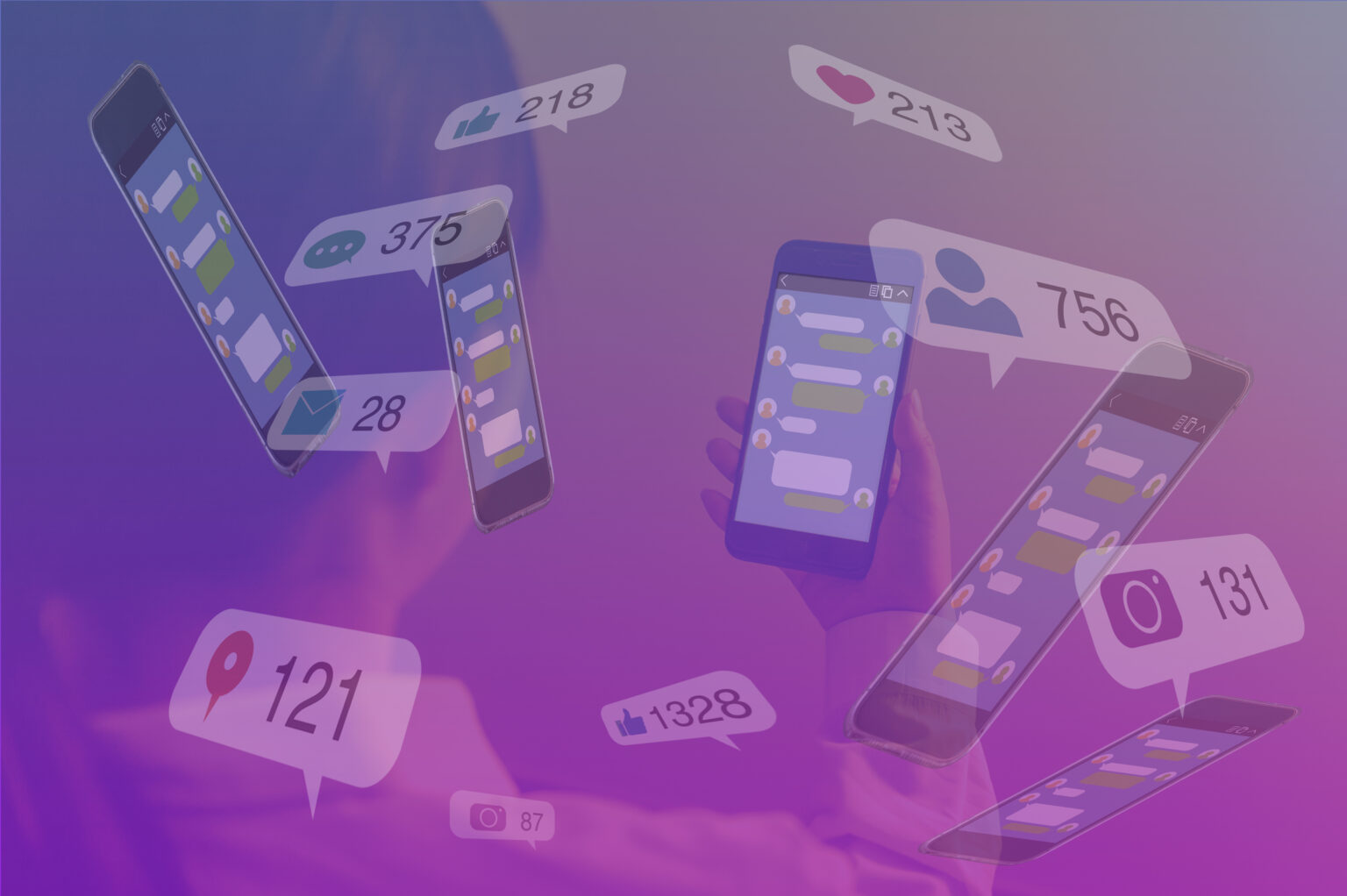
SNS依存症には特定の行動パターンが現れます。ここでは、特に代表的な特徴を5つ取り上げますので、自分や家族が当てはまらないか確認してみてください。
1.SNSが原因で睡眠時間が減る
SNSに夢中になるあまり、寝る時間が以前より遅くなったと感じることはありませんか。スマホを枕元に置いてベッドの中でも長時間SNSをチェックしてしまうと、睡眠不足を引き起こし、日中の集中力や活動能力が低下します。実際に、依存傾向にある人の7割以上が睡眠不足の問題を抱えています。
2.目の前のことに集中できない
勉強や仕事中にSNSの通知が気になって、ついスマホを見てしまう人は少なくありません。SNS依存になると、本来やるべきことよりもSNSを優先し、集中力が途切れて作業効率が著しく低下します。この状態が続くと、学業や仕事でミスが増え、生活全体に支障をきたします。
3.ちょっとした空き時間にもSNSを開いてしまう
少しの時間でもついSNSをチェックしてしまうのは依存症の兆候のひとつです。この習慣が深刻化すると、数分のつもりが何十分も画面から離れられなくなり、時間管理が困難になります。特に最近では「ドゥームスクロール」と呼ばれる、悪いニュースを無意識に延々と見続ける行動も問題視されています。
4.通知にすぐ反応しないと落ち着かない
スマホの通知が鳴ったらすぐに確認して返信しないと不安になる、という人も多いのではないでしょうか。これはSNS依存症によく見られる強迫的な行動で、「通知依存」とも呼ばれています。対人関係の不安や「取り残される恐怖(FOMO)」が背景にあり、精神的なストレスが高まる傾向にあります。
5.SNS利用を指摘されると感情が不安定になる
家族や友人からSNSの使い過ぎを指摘されると、感情的になりやすくなるのも特徴的です。依存状態にあると、自分自身を否定されたような感覚になり、怒りや悲しみを抑えられなくなります。ネット上の匿名性に慣れ過ぎると、現実の人間関係に対する感受性が低下し、感情のコントロールが困難になるのです。
SNS依存の特徴が明確になったところで、具体的な改善方法について確認しましょう。
SNS依存症を改善するために効果的な対処法

SNS依存症は、症状を自覚した時点から意識的に対策を始めることで改善が期待できます。実際に取り組める効果的な方法をいくつか紹介しますので、生活に少しずつ取り入れてみましょう。
また、ご家族や周囲の人に依存の傾向が見られる場合には、強制的ではなく、提案や話し合いの形で協力することが大切です。
デジタルウェルビーイング機能を活用する
スマホには、利用時間を管理するためのデジタルウェルビーイング機能が標準搭載されています。たとえばiOSではスクリーンタイム機能があり、特定のアプリの利用時間を制限できます。
Androidにもフォーカスモードやファミリーリンクなど、SNSの使いすぎを防ぐ仕組みが用意されています。これらを積極的に活用して、自動的にSNSの利用時間を減らしていく方法が有効です。
就寝前のスマホ利用をやめる
睡眠の質を改善するには、寝る1〜2時間前にはスマホやインターネットの利用をやめることが効果的です。スマホを寝室に持ち込まないなど、物理的な距離を作ることで、自然とSNSへの依存を軽減できます。スマホを離れた時間を読書やストレッチなど、リラックスできる時間に充てるのもおすすめです。
家族や友人と実際に会話する時間を増やす
SNS依存の背景には、対面でのコミュニケーション不足があることが多いため、リアルな人間関係を積極的に築くことが重要です。
家族や友人と一緒に食事をしたり、テレビを見ながら会話したり、挨拶をしっかり交わすだけでも効果があります。実際に顔を合わせたコミュニケーションが増えることで、SNSに過度に依存しなくても安心感を得られるようになります。
スマホ以外の趣味や楽しみを見つける
SNSにのめり込む原因の一つは、他に興味を引くものがないためです。趣味や新たな楽しみを見つけることは、SNS依存の克服にとても効果的です。ウォーキング、料理、園芸、手芸、読書など、スマホ以外の楽しい活動を見つけることで、自然とSNSを見る頻度が減っていきます。
不安が強い場合は専門機関を利用する
もしSNS依存症が深刻化しており、自力での改善が難しいと感じる場合は、専門機関の受診や相談も視野に入れましょう。
近年、ネットやゲーム依存に特化した心療内科や専門外来が増えています。久里浜医療センターなど、依存症に特化した医療機関では、対面診療のほかオンライン相談も行っているので、早めにプロのサポートを受けることも大切です。
こうした具体的な改善策を生活に取り入れることで、徐々にSNSへの依存状態を脱することが可能です。
SNSとの上手な付き合い方を身につける

SNSは便利で生活を豊かにするツールである反面、過度な利用は心身の健康や日常生活に多くの悪影響を与えます。そのため、依存状態に陥らないためには「SNSと適度な距離を保つ習慣」を身につけることが重要です。
最近では、「取り残される恐怖(FOMO)」の対極として、「あえて情報から離れる喜び(JOMO:Joy of Missing Out)」という考え方が注目されています。SNSをチェックする回数を意識的に減らし、その分、家族や友人と過ごす時間や趣味を楽しむ時間を大切にするというスタイルです。このようなポジティブな考え方を取り入れることで、無理なく自然に依存状態から離れることができます。
現代社会においてSNSを完全に避けることは難しいですが、利用時間や頻度を自分自身でコントロールする習慣を身につけ、SNSの良い面を活かしながら生活の質を高めていきましょう。











