目次
親の言葉は子どもの心に深い影響を与える

子育ては毎日の積み重ねです。何気なく子供にかけている言葉が、実は子供の将来を大きく左右することをご存知でしょうか。
特に幼少期(0~6歳)は子供の脳や心が急激に発達する重要な時期です。この時期に親が発する言葉は、子供が自分自身をどう見るか、どんな大人に成長するかに深く関わってきます。
例えば、「あなたは何をやってもダメね」という言葉は、子供が自分の能力に限界を感じ、挑戦する気持ちを失ってしまう原因になります。また、「お兄ちゃんはできるのに」という比較の言葉は、子供の心に強い劣等感を植え付けます。
さらに最近の研究によると、親から繰り返し否定的な言葉を聞いて育った子供は、大人になっても自己肯定感が低く、ストレスに弱くなる傾向があります。子供が自分自身を前向きに捉えられるようにするためにも、親が発する言葉には注意が必要です。
この記事では、親が子供に絶対に言ってはいけない言葉と、その言葉がなぜ悪影響を与えるのかを詳しく解説していきます。
子供に絶対言ってはいけない20の言葉

子供への言葉かけは、日常生活の中で無意識に行ってしまうことがあります。しかし、些細な一言が子供の心を大きく傷つけ、成長を妨げる原因となることがあります。この章では特に注意したい言葉とその理由を丁寧に解説していきます。
1. 「お兄ちゃん(お姉ちゃん)はできるのに」と他の子と比較する言葉
他の子供と比較されると、子供は「自分は劣っている」と感じ、自信を失ってしまいます。また、兄弟姉妹との関係にも悪影響を与えます。比較されることで、自分の価値を信じられなくなり、新しい挑戦や積極的な行動を避けるようになる場合があります。
子供はそれぞれ個性や成長速度が異なるため、一人ひとりを尊重し、過去のその子自身との成長を比較して褒めることが大切です。
2. 「なんでそんなこともできないの?」と問い詰める言葉

この言葉は子供の努力を否定し、「自分は能力が低い」と感じさせてしまいます。さらに、「どうせ自分にはできない」と諦める気持ちを植えつけ、挑戦意欲を失わせます。
子供が失敗したときは、なぜできなかったのかを一緒に考え、解決方法を探すことで子供の自立心や問題解決力を育むことができます。
3. 「泣くな」「そんなことで怒るな」と感情を否定する言葉
感情を否定されると、子供は自分の本当の気持ちを表現できなくなり、ストレスをため込みます。感情を出さないことが習慣化すると、心の健康や人間関係にも悪影響が出ます。
感情を抑圧せず、「悲しかったね」「悔しかったんだね」と共感の言葉をかけることで、自分の感情を理解し適切に表現する方法を学べます。
4. 「バカ」「ダメな子」と人格を否定する言葉
人格を否定する言葉は、子供の自己肯定感を深刻に傷つけ、「自分は愛される価値がない」と感じさせます。一度傷つけられた自己イメージは簡単に回復せず、大人になっても自信を持てない原因になります。
人格に触れるのではなく、行動のどこが良くなかったのかを具体的に指摘するよう心がけましょう。
5. 「産まれてこなければよかった」と存在を否定する言葉
存在を否定する言葉は最も深刻な心理的ダメージを与えます。子供は親に認められ、愛されることで自分自身の存在意義を確認します。親から存在そのものを否定されると、自尊心は大きく損なわれ、人生を通して回復困難なトラウマとなる場合もあります。
親は常に子供の存在を肯定し、「あなたがいてくれて嬉しい」という言葉を伝え続けることが大切です。
6. 「あなたには無理だよ」と可能性を否定する言葉
「あなたには無理」と言われると、子供は挑戦する前から諦めてしまいます。これが習慣化すると、新しいことに消極的になり、自信を失ってしまいます。
たとえ難しいことであっても、「挑戦してみよう」「一緒にやってみようか」と励ますことで、子供の意欲や自信が育ちます。子供が自分の可能性を信じられるよう、サポートする姿勢が必要です。
7. 「早くしなさい」と急かす言葉
日常的に「早くしなさい」と言われると、子供はストレスを感じ、焦りやすくなります。結果として、落ち着きを失って行動が遅れたり、ミスが増えたりする可能性があります。
時間に余裕をもたせて具体的な指示を与えたり、「時計の針がここまで来たら出かけよう」と時間感覚を教えたりすると、子供が自分のペースで動くことができ、焦らずに済みます。
8. 「どうしていつも〇〇なの?」と強調した否定の言葉
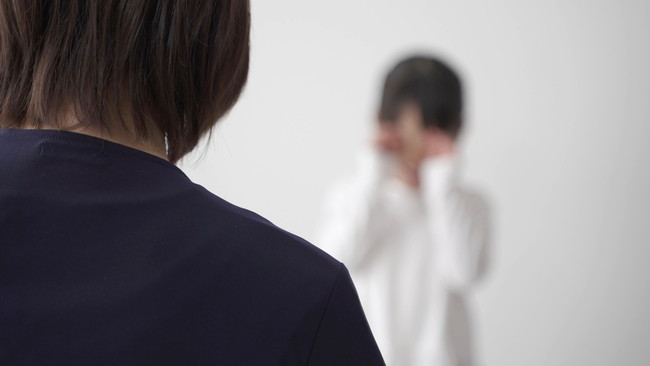
「いつも」「絶対」「ちっとも」といった極端な表現は、子供が自分の全人格を否定されたと感じる原因になります。子供は「どうせ自分はいつもできない」と自己評価が下がり、自信を持てなくなります。
具体的な場面に注目して、「今回はこうだったね」「次はどうしたら良くなるかな?」と前向きな声掛けを心がけることで、子供が自分の行動を見直し、改善していく意欲が生まれます。
9. 「男の子(女の子)なのに」と性別の決めつけの言葉
「男の子なのに泣くの?」「女の子なのに乱暴ね」など性別の決めつけは、子供の自由な感情表現や自己表現を妨げます。性別に関係なく、子供一人ひとりの個性や感情を尊重することが大切です。
「どんな気持ちだったの?」「そう感じるのは自然だよ」と子供のありのままを認めることで、自己肯定感が高まり、自分らしさを大切にできるようになります。
10. 「頑張れ」と何度も言い続ける言葉
「頑張れ」という言葉は良かれと思って使いますが、子供に過度なプレッシャーを与える場合があります。子供が常に「頑張らなければならない」と感じると、楽しんで挑戦する意欲が薄れ、失敗を恐れるようになります。
「毎日頑張ってるの知ってるよ」「努力してる姿が素敵だね」と具体的な行動を認め、適度に励ますことで、子供が安心して前向きに取り組めるようになります。
11. 「あなたのせいで」と責任を押しつける言葉
親が「あなたのせいでこうなった」と責める言葉を使うと、子供は罪悪感を抱き、自分を責めるようになります。自己否定感が強くなり、自信を失ってしまいます。
問題が起きた時は「こういうことがあったけど、次からどう気をつけようか」と冷静に対応策を話し合うことで、子供は責任を感じるのではなく、前向きな行動を身につけられます。
12. 「そんなことくらいで」と子供の気持ちを軽く見る言葉
子供が悩んだり悲しんだりしているとき、「そんなことくらいで」と軽視すると、子供は自分の感情を親に打ち明けなくなります。これは心の距離を広げ、親子関係に悪影響を及ぼします。
小さなことでも「そう感じたんだね、聞かせて」と寄り添うことで、子供は安心して自分の気持ちを話せるようになります。
13. 「うるさい」「黙ってて」と言葉を封じる表現
親が忙しいときや苛立っているときに、つい「うるさい」「黙ってて」と子供を遮ることがありますが、これを繰り返すと子供は自分の考えや気持ちを表現する意欲を失います。
また、自尊心を傷つけ、自信をなくしてしまいます。「今はお話しできないけど、後でゆっくり聞かせてね」と適切な表現を教えることで、子供のコミュニケーション能力を守れます。
14. 「また失敗?」と失敗を強調する言葉
子供が失敗をしたときにそれを強調すると、失敗を恐れ、挑戦する気持ちが弱くなります。「失敗は良くないもの」と刷り込まれてしまうため、子供は新しい経験を避けるようになります。
「失敗しても大丈夫。何ができるようになったか一緒に考えよう」と前向きな声かけをすると、子供は安心して新しいことに挑戦する勇気を持てます。
15. 「言うことを聞かないと〇〇するよ」と脅す言葉
「言うことを聞かないとおもちゃを捨てるよ」「鬼が来るよ」といった脅しは、一時的には効果があるかもしれませんが、子供に恐怖心や不安感を植えつけます。信頼関係が崩れ、子供は安心感を失います。代わりに、「どうしてこれが必要なのか」を具体的に説明し、子供自身に理解してもらうことで、主体性や判断力を育てることができます。
16. 「もう知らない」と突き放す言葉
子供の行動にイライラして、「もう知らない」と突き放すと、子供は親に見捨てられるのではないかと強い不安を感じます。安心感が奪われ、自分自身を否定されているように受け取ってしまいます。
子供に対しては、「困ったことがあれば一緒に考えよう」と寄り添う態度を見せることで、信頼関係が保たれ、親子の絆が深まります。
17. 「勉強しなさい」と一方的に命令する言葉
「勉強しなさい」という一方的な命令は、子供の勉強意欲を失わせる原因になります。強制されることで、学ぶことへの嫌悪感や反発心が芽生え、自主的に学ぶ姿勢が育ちません。
「今日は何を勉強する予定?」「難しいところがあれば一緒にやってみよう」と、自発的な行動を促す言葉かけをすると、学ぶ楽しさや意欲を引き出せます。
18. 「ちゃんとして」「しっかりしなさい」と抽象的な言葉

「ちゃんとして」という抽象的な言葉は子供を混乱させ、何をどうすれば良いのか理解できなくします。何度も言われるうちに子供は自己肯定感を失い、自信をなくしてしまいます。
「おもちゃを片付けよう」「姿勢を良くして座ろう」など、具体的で明確な言葉を使うことで、子供は行動の目標が明確になり、自信を持って動けるようになります。
19. 「あなたのためを思って」と上から目線の言葉
「あなたのためを思って」という言葉は、親の気持ちを伝えているつもりでも、子供には威圧的に聞こえることがあります。子供は自分の気持ちや考えが無視されているように感じ、反発心が強まります。
親子で対話をし、「あなたはどう思う?」と子供の意見を聞き、共感を示すことが、信頼関係を深めるためには大切です。
20. 「何回言ったらわかるの?」と責める言葉
「何回言ったらわかるの?」と繰り返し言われると、子供は自分の能力や記憶力を疑うようになり、失敗を極度に恐れるようになります。問題点を明確に示し、「次にこういう場面があったら、こうしてみようね」と具体的に伝えることで、子供は失敗を学びの機会と捉えられるようになり、成長を促せます。
まとめ

子供への言葉は、大人が想像する以上に強い影響力を持っています。日々の何気ない一言が、子供の心に一生残る傷になることもあれば、逆に生涯を支える励ましにもなります。
親が子供に対して持つべきは「完璧な言葉遣い」ではなく、「子供の気持ちを理解し、尊重しようとする姿勢」です。言葉を通じて愛情を伝え、子供が自信を持って自分らしく生きていけるよう支えることが、親としての最も大切な役割です。











