目次
性格は人それぞれ!幼児期の経験や実感がカギ

性格は人それぞれ大きく異なり、おおらかで感情的になりにくい人もいれば、些細なことで感情が揺れやすい人もいます。また、ポジティブ思考が得意な人もいれば、物事を悲観的に捉えがちな人もいます。この違いはどこから来るのでしょうか?
心理学では、性格は幼児期の経験や環境からの影響を受けて形成されるとされています。具体的には、親から受ける愛情の深さや育児方針、友人との関係、遊びを通じた社会的な学びが重要な役割を果たします。
近年はメディアの刺激も大きな影響に
さらに、近年はデジタルメディアの発展が子どもの性格形成に与える影響が注目されています。スマホやタブレット、YouTubeなどのメディアが、子どもの好奇心や興味に働きかける一方で、過剰な刺激や時間の使い方により負の影響を及ぼす場合もあります。
こうしたメディア利用の良し悪しは、内容の質と時間のバランス次第です。親が適切に見極めて子どもに与える環境を整えることが、健全な人格形成に寄与するとされています。
性格は何歳までに決まる?

性格は成長のどの段階で形作られるのでしょうか。
人格の土台形成は6歳頃まで
心理学や教育学の分野では、0~6歳が人格の土台を形成する最も重要な時期とされています。この期間は、脳の成長が著しいことから「ゴールデンエイジ」とも呼ばれることがあります。この時期に子どもが経験する親の態度や周囲の人々との関わりが、性格形成に大きな影響を与えるとされています。
6歳までの間に人格の土台のおおよそ8割が形作られるという主張もあります。この土台は主に、親から受ける愛情や安心感を基盤としています。たとえば、愛情豊かな言葉かけや親が見守りながらも自由に行動させる環境は、子どもの性格をポジティブに形成する要因になります。また、幼稚園や保育園での友人関係も、協調性や社会性を学ぶうえで欠かせない要素です。
性格の基本が決まるのは10歳まで
6歳までに形成された人格の土台は、その後の経験を通じて色濃く変化していきます。10歳頃までには性格の基本部分がほぼ決まるとされています。この段階では、学校生活や友人関係が大きな影響を与えます。たとえば、成功体験や失敗体験を通じて得られる自己肯定感やストレス耐性は、この時期に培われることが多いです。
一方で、性格が完全に固定されるわけではありません。10歳以降も、教育方針や生活環境、他人との新たな交流によって変化する可能性があります。したがって、親や教師が子どもの長所を引き出す環境を提供することが重要です。
親や周囲の人からの影響が性格形成に与える役割

性格形成には、親や周囲の人々からの影響が極めて大きいことがわかっています。特に、0歳から6歳の時期に親がどのように接するか、どれだけの愛情を注いでいるかが、子どもの性格に多大な影響を与えます。この期間に親が子どもの意思を尊重しながら正しい愛情を示すことが、子どもの心の安定や自己肯定感を育む基盤となります。
具体的には、次のような接し方が性格形成を良い方向へ導きます。
- ポジティブな言葉がけを意識する:失敗を責めるのではなく、成功体験を褒める。
- 否定的な言葉を避ける:子どもの感情や意見を否定せず、受け入れる姿勢を持つ。
- 自由で安心できる環境を整える:心の余裕を持てる生活環境を提供する。
これらの要素が、子どもの性格形成に大きく寄与します。一方で、過剰な干渉や過度なプレッシャーは、ストレスや不安感を生み、性格形成に負の影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
10歳以降でも性格は変えられる?

10歳を過ぎた後や成人後でも、性格を変えることは可能です。10歳までに形成される性格の「土台」はその人の基本的な傾向を決定しますが、性格全体の半分程度にすぎません。残りの部分は後天的な要素に影響され、変化の余地が十分にあります。
心理学の研究によれば、性格を変えるためには次のような方法が効果的とされています。
- 付き合う人を変える:
ポジティブな影響を与える人と交流することで、考え方や行動に良い変化をもたらす。 - 理想の人物像を意識する:
目標となる人物と同じ行動を取り入れることで、少しずつ理想に近づける。 - 環境を変える:
職場や住環境を大きく変えることで、新しい刺激を受け、性格にも変化が現れる。 - 日常的な行動を変えてみる:
意識的に新しい習慣を取り入れることで、新たな思考パターンが形成される。
たとえば、常に否定的な発言をする人と交流を続けていると、自分の思考も否定的になる可能性があります。一方で、明るくポジティブな人と関わると、自身の考え方も徐々にポジティブになっていくことが期待できます。
努力で性格を変えることは可能!

性格は固定されたものではなく、環境や経験、本人の努力次第で変えることができます。ただし、変化を実現するためには一定の覚悟と継続的な取り組みが必要です。特に以下のポイントを押さえることが重要です。
- 現状を客観的に把握する:自分の性格のどこを変えたいのか、明確にする。
- 目標を設定する:どのような性格になりたいのかを具体的にイメージする。
- 日々の積み重ねを大切にする:小さな変化を積み重ねることで、大きな変化へとつながる。
心理学者は「行動が先、感情が後」と述べています。つまり、新しい行動を取ることで、それに応じて性格や考え方が変化していくという理論です。自分の理想とする性格に近づくために、日常生活の中で積極的に変化を取り入れてみましょう。
ポジティブな習慣で性格をより良い方向に!
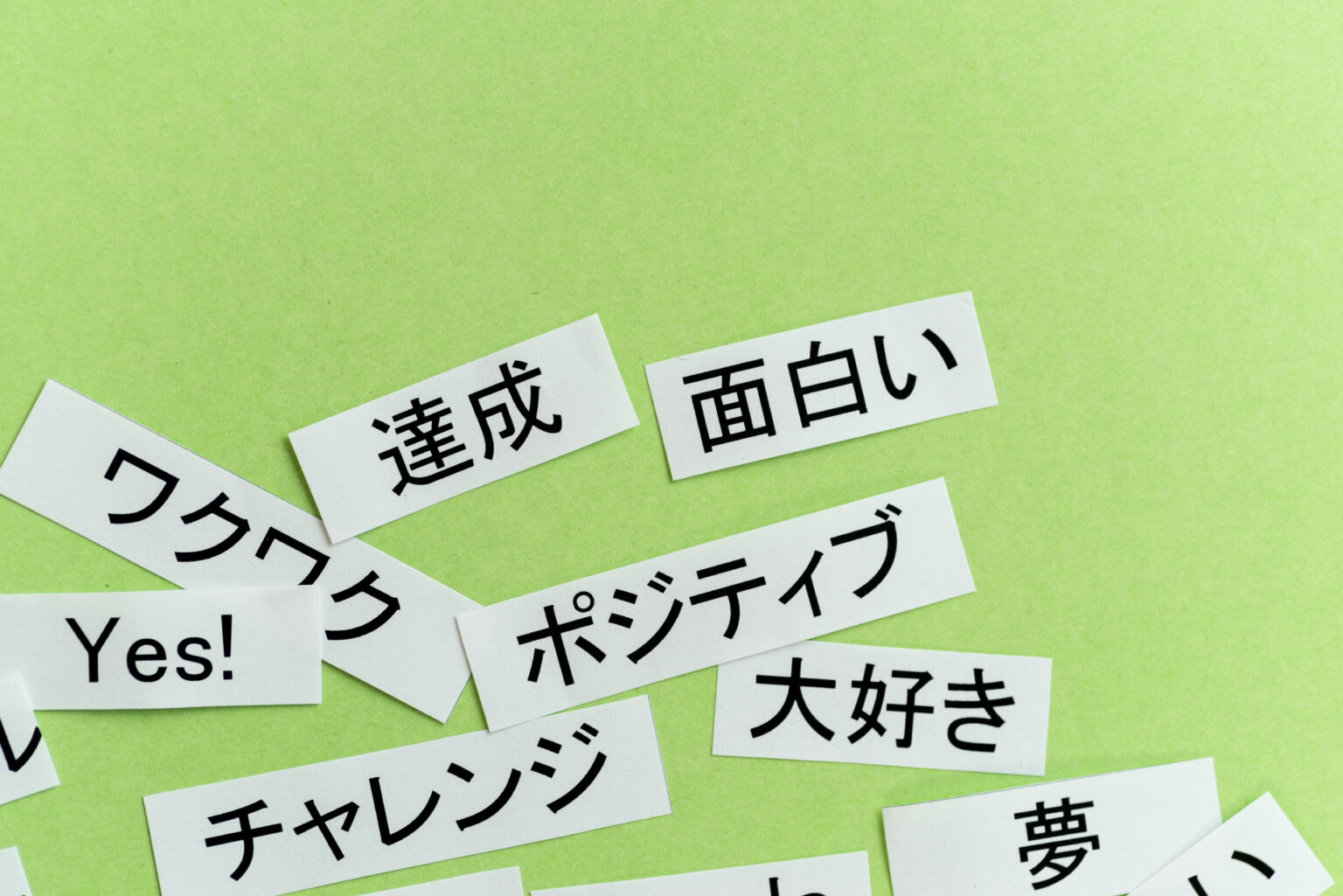
性格は、幼少期に大きく形成される一方で、成人後でも変えることができます。0歳から6歳までの間に愛情や適切な環境を受けることが、性格の土台をつくり、10歳までには基本的な傾向が固まると言われています。しかし、その後も経験や環境の変化を通じて、性格は柔軟に変化する可能性を秘めています。
性格を変えたいと思ったときは、自分の行動や環境を意識的に変えることが鍵です。理想の自分をイメージしながら、ポジティブな習慣を取り入れ、努力を積み重ねることで、性格をより良い方向へと変えることが可能です。











