目次
LED電球と白熱電球の電気代を比較
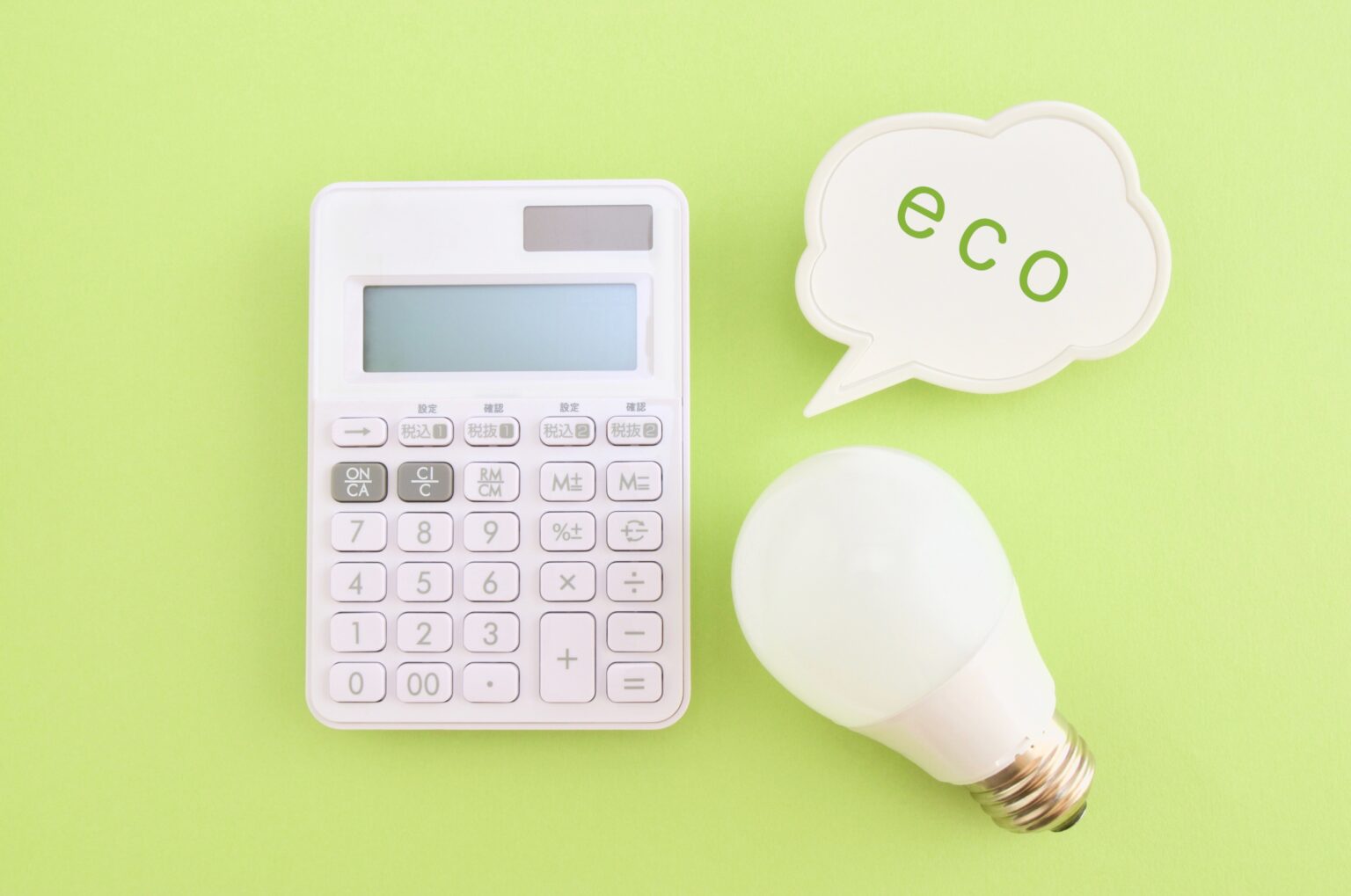
「LED電球は電気代が安い」と耳にすることは多いですが、具体的にどのくらい差があるのかを知る人は少なくありません。
ここでは、家庭でよく使われる60Wの白熱電球と、それと同等の明るさを持つLED電球(消費電力約8〜9W)を例に、実際の電気代を比較してみます。
1時間・1日・1年の電気代の差
電気代は「消費電力(kW)× 使用時間(h)× 電気料金(円/kWh)」で計算できます。1kWhあたり27円と仮定して計算すると次のようになります。
- 白熱電球(60W):1時間あたり約1.62円
- LED電球(9W):1時間あたり約0.24円
この差は小さく見えるかもしれませんが、1日8時間使うと白熱電球は約13円、LED電球は約1.9円。年間に換算すると白熱電球は約4,745円、LED電球は約701円となり、年間で4,000円以上の差が生まれます。
LED電球が白熱電球より消費電力が少ない理由

白熱電球はフィラメントを高温にして光を出す仕組みですが、その際に電気エネルギーの大半が熱となって失われます。つまり、光よりも熱を作るために電気を使っているのです。
一方、LED電球は半導体に電流を流して直接光を生み出す仕組み。余分な熱がほとんど出ないため、少ない電力で同じ明るさを実現できます。これが電気代の大幅な節約につながる本質です。
つけっぱなしにした場合のコスト差
電気を24時間つけっぱなしにすると差はさらに広がります。
- 白熱電球(60W):1日で約39円、1か月で約1,166円
- LED電球(9W):1日で約6.5円、1か月で約194円
つけっぱなしが続くと、1か月で約1,000円、年間では1万円以上の差に。特に廊下や玄関など消し忘れが起こりやすい場所では、LED電球のメリットが顕著に表れます。
家庭での使い方と電気代の違い

数字だけの比較では実感がわきにくいものです。ここでは、家庭のさまざまな場面を想定しながら、LED電球と白熱電球でどれくらい電気代が違うのかを考えてみましょう。
リビングや廊下など日常のシーンでの差
リビングは1日数時間、家族が集まる時間帯に照明をつけることが多い場所です。
白熱電球を使うと、毎日数時間の積み重ねで年間数千円単位の電気代になります。これをLED電球に変えると、同じ明るさで電気代を約80%削減できます。
また、廊下や階段などは「点けっぱなしになりやすい場所」です。夜間の安全のために常に点灯している家庭もありますが、LEDなら電気代を抑えながら安心を確保できます。
白熱電球を使い続けると年間で数千円以上の差がつくため、こうした場所は優先的にLEDに切り替える価値があります。
豆電球をLEDにした場合のコスト
常夜灯として使う豆電球は、消費電力が1W以下と小さいため、もともとの電気代はわずかです。1日中つけっぱなしでも年間数百円程度にしかなりません。LEDに変えればさらに安くなりますが、節約効果としては限定的です。
そのため、コスト削減を考えるなら、まずは使用時間が長いリビングや玄関、廊下の照明をLED化するほうが効果的です。豆電球をLEDに変えるのは、明るさや寿命を考慮して利便性を重視するケースが向いています。
電気のオンオフが寿命や電気代に与える影響
「電気はこまめに消したほうがいい」と言われますが、白熱電球とLED電球では事情が異なります。
白熱電球は点灯と消灯を繰り返すことでフィラメントに負担がかかり、寿命が短くなります。一方、LED電球はオンオフによるダメージがほとんどないため、こまめに消すことが推奨されます。
つまり、LED電球を使う場合は「必要なときだけ点ける」という使い方が電気代の節約にも寿命の延長にもつながります。センサー付きのLEDを導入すれば、消し忘れを防ぎつつ無駄な電気代を抑えることもできます。
LED電球の寿命と上手に使うポイント

LED電球は「電気代が安い」だけでなく「寿命が長い」ことも大きな特徴です。白熱電球と比較すると、その差は歴然としています。
ここでは寿命に関する基本知識と、LEDをより長く使うための工夫を解説します。
LED電球と白熱電球の寿命の違い
一般的なLED電球の寿命は約40,000時間とされています。
1日6時間使用した場合、単純計算で18年以上使える計算になります。一方で白熱電球の寿命は約1,000〜2,000時間、毎日6時間使えば数か月から1年程度で交換が必要です。
つまり、LED電球は白熱電球の20倍以上長持ちすることになります。交換の手間が減るだけでなく、電球の購入費用そのものも抑えられるため、電気代と合わせて総合的なコスト削減につながります。
寿命を縮めないために気をつけること(熱・設置環境)
LED電球は熱に弱いという特徴があります。白熱電球に比べて発熱は少ないものの、放熱がうまくできない環境で長時間使うと内部が高温になり、寿命が縮んでしまいます。
特に注意が必要なのは、浴室や玄関などの密閉型照明器具での使用です。対応していないLED電球を使うと熱がこもり、想定より早く劣化する可能性があります。「密閉型器具対応」と記載されている製品を選ぶことが大切です。
また、断熱材に囲まれたダウンライトに使う場合も同様で、対応製品を選ばなければ寿命を縮めてしまう原因になります。
LEDがうっすら点灯する現象と電気代への影響
スイッチを切ったのにLED電球がうっすら光ることがあります。これは「ゴースト点灯」と呼ばれる現象で、配線やスイッチ内部で微弱な電流が流れていることが原因です。
この現象は見た目に気になることはありますが、消費電力はごくわずかで、電気代に与える影響はほぼゼロです。どうしても気になる場合は、ゴースト点灯に対応したLED電球を選んだり、電気工事でスイッチを交換することで解消できます。
電気代を節約できるLED電球の選び方

LED電球はどれを選んでも白熱電球より電気代は安くなりますが、商品によって性能や使い勝手は大きく異なります。
選び方を間違えると期待したほどの節約効果が得られないこともあるため、購入前に押さえておきたいポイントを紹介します。
明るさの見方(ルーメンとワット相当)
白熱電球は「ワット数」で明るさを判断していましたが、LED電球では「ルーメン(lm)」が基準になります。
例えば、白熱電球60Wに相当する明るさは約810lmです。パッケージに「60W相当」と表記されていることも多いので、ルーメン値と合わせて確認しましょう。必要な明るさを正しく選ぶことが、快適さと節約の両立につながります。
光の色を選ぶ(電球色・昼白色・昼光色)
LED電球は色味のバリエーションが豊富です。温かみのあるオレンジ系の「電球色」、自然な光に近い「昼白色」、青みがかった「昼光色」などがあります。
リラックスしたい寝室は電球色、勉強部屋や作業スペースは昼光色など、場所や用途に合わせて選ぶと暮らしが快適になります。間違った色を選ぶと不必要に明るくしてしまい、無駄な電気代につながることもあるため注意が必要です。
部屋に合った配光角度を選ぶ
LED電球は光の広がり方を示す「配光角度」が製品によって異なります。
リビング全体を照らしたい場合は光が広がる「広配光タイプ」、スポット的に照らしたい場合は「集光タイプ」を選びます。用途に合った配光角度を選ぶことで、必要以上に多くの電球を点けずに済み、電気代の節約効果が高まります。
価格と性能のバランスをどう考えるか
LED電球は価格帯が幅広く、安い製品もあれば高性能モデルもあります。安価なものは初期費用を抑えられますが、寿命や明るさが安定しないケースもあります。
一方、有名メーカーの製品はやや高価ですが、寿命が長く発光効率も高いため、結果的にコストパフォーマンスが優れることが多いです。長期的に見れば、信頼できる製品を選ぶほうが節約につながります。
まとめ

LED電球は白熱電球に比べて電気代が大幅に安く、寿命も長いため総合的なコストパフォーマンスに優れています。しかし、効果を最大化するには明るさや色、配光角度、設置環境に合った商品を選ぶことが欠かせません。
また、センサー付きや調光対応など機能性を重視すれば利便性も高まります。数字の節約効果だけでなく、自宅の生活スタイルに合ったLED電球を選ぶことで、快適さと経済性を同時に得ることができます。











