目次
色と日本の暮らしの関係

日本では昔から、色には特別な意味があると考えられてきました。お正月には紅白の飾り、結婚式には金や銀など、色は生活のさまざまな場面で使われています。また、「この色は縁起が悪い」と避けられる色も存在します。さらに最近では、色を風水と結びつけて運気を上げようと考える人も増えてきました。
色が運気に影響を与えるというのは、日本だけでなく、中国から伝わった風水の考え方も関係しています。風水では、「気」と呼ばれる見えないエネルギーが暮らしに影響を与えると考え、その流れを整えるために色を利用します。
ここからは、日本で伝統的に良いとされる色や注意が必要な色について、文化的背景や風水的な考え方とともに詳しく説明していきます。
日本で縁起の良い色とは?

日本では、特定の色が縁起が良いとされ、祝いの席や特別な行事に頻繁に使われます。それぞれの色には深い意味があり、ただの飾りではありません。それぞれの色がなぜ縁起がいいのかを理解すると、より効果的に取り入れることができます。
紅白
日本で最も知られる縁起の良い色は紅白(赤と白)です。紅白は祝いごとの象徴として広く親しまれています。紅は血液や太陽を連想させ、生命力や活力を意味します。白は清潔さや純粋さを表し、新しい出発や再生を意味します。
この二つが組み合わさることで、「喜び」と「清らかさ」の調和を象徴し、おめでたいと考えられています。
- 結婚式や正月飾りなど、祝いの場で使用
- 紅白幕や紅白餅などで喜びを表現
- 古代から日本文化に根付いている伝統的な配色
紅白は日本人の生活の中に深く浸透しており、縁起が良い色の代表格とされています。
金色と銀色
金色と銀色も、日本文化の中で縁起が良いとされる色です。特に金色は富や繁栄を意味し、銀色は清浄さと調和を表します。金銀を組み合わせることで、豊かな繁栄と落ち着きを同時に表現することができます。
- 金色は仏像や神社の装飾、祝いごとの飾りに多用される
- 銀色は高貴さや美しさを示し、儀式や装飾に好まれる
- 結婚式や新年飾りなどの特別な場面で多く見られる
金銀は高貴さと豪華さを備えつつ、縁起を担ぐ色として、非常に価値があるとされています。
橙色(だいだい)
橙色も、日本では古くから縁起の良い色として親しまれています。その名前の由来は「代々栄える」という言葉に通じており、家系の繁栄や子孫繁栄の願いを込めた色とされています。
- 鏡餅の上に橙の果実を飾り、子孫繁栄を願う
- 家庭の平穏と繁栄を願う色として、お正月の飾りに好まれる
- 温かみのある色で、家族の絆を象徴する
橙色は家庭運や子孫運を高める色として、特に正月など家庭行事に取り入れられることが多い色です。
緑色
緑色は生命力や健康を象徴し、縁起が良いとされています。日本では松や竹の色として知られ、不老長寿や健康の象徴として伝統的に用いられてきました。
- 門松など正月飾りに使用され、不老長寿を願う
- 日常生活でも観葉植物などで健康運を高める色として利用
- 目に優しくリラックス効果もあるため、家庭での利用が多い
緑は日本文化でも風水でも、健康や長寿、家庭の安定を願う色として広く推奨されています。
紫色
紫色は日本において古くから高貴な色とされ、縁起の良さを象徴します。聖徳太子が定めた冠位十二階では最高位の色とされており、尊敬や敬意の意味があります。
- 古来より貴族や僧侶など特別な人だけが使える色だった
- 厄除けや魔除けの意味もあり、品格を示す色
- 落ち着いた色調が精神的な安定をもたらすとされる
紫色は格式高い縁起の良い色であり、アクセントカラーとして取り入れると運気が向上すると言われています。
日本で縁起の悪い色とは?
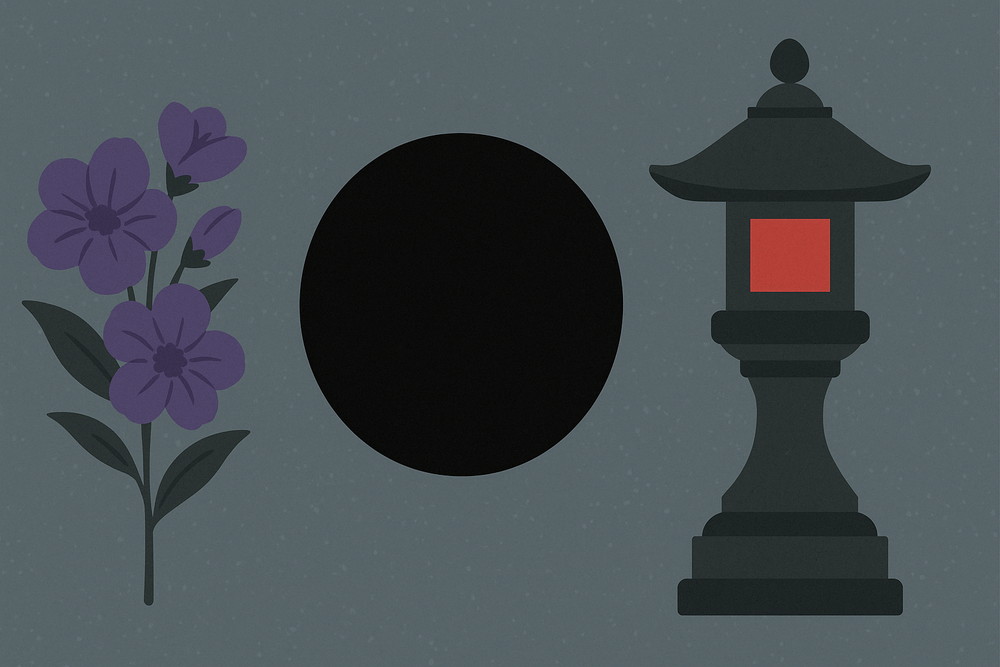
縁起が悪いとされる色は、日本の文化的背景や生活習慣の中でのイメージによるところが大きいです。絶対に使ってはいけない色というわけではありませんが、使い方や場面によっては注意が必要です。
それぞれの色がなぜ縁起が悪いと感じられるのかを詳しく見てみましょう。
黒色
日本で縁起が悪い色としてまず挙げられるのが黒色です。黒は喪服の色として知られ、「死」や「別れ」といったイメージが強く結びついています。また、「腹黒い」という言葉があるように、不正や悪意を連想させる場合もあります。
- 葬儀や弔事に用いるため、「悲しみ」や「別れ」を象徴する
- インテリアで多用すると陰気な雰囲気になりやすい
- 一方で、高級感や威厳、魔除けとしての役割もあり、差し色として使うと効果的
黒は負のイメージを持たれやすい一方、使い方次第で品格を高める色でもあるため、使う場面や配分を慎重に考える必要があります。
白色
白色は清潔さや純粋さを象徴し、祝いの場でも用いられますが、同時に葬儀での死装束に使われることから縁起が悪いと感じる場面もあります。日本では死者を弔う際に白装束を用いる習慣があり、「死」や「終わり」を連想させることもあるのです。
- 葬儀や病院などで使われる色であるため、場合によっては避けるべきとされる
- 結婚式の白無垢など祝い事では吉とされる両義性を持つ
- 空間に全面的に使うと冷たく、緊張感を感じさせるため、配分に注意が必要
白色は状況次第で良くも悪くも解釈されるため、使う場面を選ぶ必要があります。ポイントで他の色と組み合わせるのが良いでしょう。
紫色
紫色は日本では高貴さを示す縁起の良い色ですが、一方で葬儀や法事の花にも多く用いられるため、死や哀悼のイメージも持っています。このため、紫色の使い方には注意が求められる場合があります。
- 葬儀や供花に使われ、悲しみや哀悼の印象を与えやすい
- 特に濃い紫は、暗く重い印象を与える可能性がある
- 淡い紫やラベンダーカラーは柔らかい印象で縁起が悪いとされることは少ない
紫色は、高貴な印象と悲しみの印象が混在するため、状況や色合いに配慮して取り入れることが重要です。
グレー(灰色)
グレー、特に濃い灰色は日本において縁起が悪いとされることがあります。その理由は、曖昧さや憂鬱な気分を連想させる色合いにあります。特に祝いの場では使われないことが多く、気持ちを沈ませる印象を与えやすいのです。
- 喪服として使われることがあり、葬儀や弔事の色として認識されることがある
- 暗く曖昧な色合いは陰気な印象を与える可能性がある
- 明るめのグレーは落ち着きや調和の印象を持つため、ポイントで使うのは問題ない
グレーは場面によっては注意が必要ですが、落ち着きのある色でもありますので、明るさを調整して使うと良いでしょう。
真っ黄色(鮮やかすぎる黄色)
意外に感じるかもしれませんが、鮮やかすぎる真っ黄色は日本の風水的に縁起が悪いとされる場合があります。特に財布の色として真っ黄色を使うと、お金が外へ出ていくという説もあり、注意が必要な色です。
- 派手すぎる色合いが浪費や散財を連想させる
- 目立ちすぎるため、場によっては敬遠される可能性がある
- 淡い黄色やクリーム色は金運アップとされるが、鮮やかすぎる黄色は避けた方が良いとされる
黄色系は基本的に縁起の良い色ですが、濃度や鮮やかさによって印象が大きく異なります。落ち着いた色調を選ぶのが無難です。
まとめ
色の縁起の良し悪しは固定されたものではなく、状況や文化的背景によって意味が変わります。実際、江戸時代以前の日本では、黒は格式高い色として武士に愛用されていました。また、白は死を象徴すると同時に、新たな出発や純粋さも表します。
大切なのは、その色を使う目的や場所を理解し、色をうまく生活に取り入れることです。特に、色選びで迷ったときは自然に近い色(淡い色やアースカラー)を基調にすると、人に安心感を与えやすくなります。











