目次
冷蔵庫の中身、スカスカとパンパンどっちがいい?

毎日のように開ける冷蔵庫の扉。「なんかいつも食材でパンパンかも…」と感じたり、「スカスカにすると、逆に冷えにくくなりそう」と不安になったりしませんか?
筆者自身も以前は「食品が多いほど無駄なく使っている気がする」と思っていましたが、実際はその逆で、ぎゅうぎゅう詰めは節約の大敵になることも多いのです。
冷蔵庫には主に2つのスペースがあります。一つは普段よく開け閉めする冷蔵室。野菜や飲み物、日常的な食品を保存する場所です。
もう一つは冷凍室で、こちらはアイスや冷凍食品を凍らせて保存する場所ですね。この二つ、実は詰め方ひとつで電気代が大きく変わるのです。
この記事を読めば、冷蔵庫の使い方ひとつで電気代が節約できることが分かりますよ。
冷蔵庫の中身で電気代が変わる理由

冷蔵庫は、中にある食品を決められた温度で冷やすために、常に電気を使っています。そのため、冷気がどれだけ効率よく庫内を回れるかが重要なのです。
冷蔵室がスカスカの状態だと、冷気がすっと流れ、効率よく庫内が冷えます。逆に冷凍室の場合は、食品が多く詰まっている方が食品同士が冷やし合い、保冷効果を発揮します。
こうした基本的なポイントを押さえることで、毎月の電気代に少しずつ差が生まれてきます。実際にどんな詰め方が節約に理想的なのか、このあとじっくり説明していきますね。
冷蔵室は「スカスカ」が理想

冷蔵室に食品がぎっしり詰まっていると、充実感はありますが、実はあまり効率がよくありません。
特に、買い物の後に食材を詰め込んでしまいがちな家庭では、「いつの間にか奥に賞味期限切れの食品が眠っていた…」なんて経験がある方も多いのではないでしょうか。
また、食品を入れすぎると奥のほうに何が入っているかわからなくなり、無駄に食品を買い足してしまうこともありますよね。
食品を減らしてスカスカな状態にすると、そんな無駄を防ぎつつ、電気代の節約にも繋がるんです。
冷蔵室がスカスカだと節電できる仕組み
冷蔵室の中がスカスカだと、冷気の通り道がスムーズになります。これは、混雑している道路と空いている道路を想像すると分かりやすいですね。
車が渋滞していると目的地に着くまでに時間がかかりますが、空いている道ならすいすい進めます。同じように、食品が少ないスカスカの冷蔵室は、冷気がスムーズに流れるため、無駄な電気を使わず効率よく冷やすことができます。
毎日使う冷蔵室だからこそ、この「スカスカ状態」が実現できるよう、収納を少し工夫してみましょう。
冷蔵室をスカスカにするテクニック
冷蔵室をスカスカに保つコツは、とてもシンプルです。まずは冷蔵室内の食品をカテゴリごとに分けて収納することを意識します。「調味料エリア」「野菜スペース」「飲み物ゾーン」などと、区画をきっちり決めておくのがポイントです。
また、冷蔵室内の見通しをよくするためには、「7割収納」を目指しましょう。棚板やケースを使って食品を縦に並べると、意外なほど空間が広がりますよ。
私自身、いつも食品をたくさん買い込んでしまい、冷蔵室がパンパンでしたが、「使いかけの食品をなるべく前に並べる」というルールを作ってからは食品ロスも減りました。食品ロスを減らせると、結果的に食費も抑えられるので一石二鳥ですよね。
また、冷蔵室のドアポケットには牛乳やジュースなど、背が高い飲み物だけを入れ、小さな食品を置かないこともポイントです。取り出しやすく、見やすい収納を心がければ、自然に庫内はスカスカを維持できます。食品の整理がスムーズになると、毎日の生活もぐっと快適になりますよ。
冷凍室は「パンパン」がベスト

冷凍室は、冷蔵室とは逆で、食品をぎゅうぎゅうに詰めた状態の方が節約に適しています。
実は、冷凍室は食品が隙間なく詰まっている方が、食品同士が冷やし合い、温度が安定するのです。イメージとしては、たくさんの氷をぎっしり詰めたクーラーボックスのような状態です。食品それぞれが保冷剤の役割をしてくれるんですね。
そのため、冷凍室にすき間が多いと、逆に冷気が逃げやすく、食品を冷やすために多くの電力がかかってしまいます。
食品同士が冷やし合うメリット
冷凍室の中を食品でパンパンに詰めると、食品同士が冷やし合って温度が安定しやすくなります。
イメージとしては、冷凍食品が互いに「冷気のバトンタッチ」をする感じです。例えば冷凍肉の隣に冷凍ごはん、その隣に冷凍野菜という具合に、食品が密着していれば、扉を開けたときも温度が急激に変わりにくいのです。
実際、私も冷凍室を整理整頓しつつ食品を多めに入れるようにしたら、いつもよりアイスが溶けにくくなったと感じました。電気代も気になりますが、食品がしっかり冷えることは大切ですよね。
とはいえ、ただ闇雲に食品を詰めればいいわけではありません。詰め方を少し工夫するだけで、食品の持ちや使いやすさも変わりますよ。
食品を詰め込む際の注意点
冷凍室をパンパンにするときに気をつけるべきは、「冷凍焼け」です。
冷凍焼けとは、食品の水分が抜けて乾燥し、食感や味が悪くなることを言います。開封済みの食品をそのまま袋ごと入れると起きやすいんですよね。
防ぐコツとしては、
- 開封済みの食品は、ジップ付きの保存袋やラップに包んで保存する
- 食品のパックには日付を書いて期限を管理する
- 冷凍庫専用の整理ボックスを使い、食品の管理をしやすくする
こうした工夫をすると、食品の味も守れて、食費の節約にもつながります。少しの手間で大きなメリットがあるので、試してみる価値ありです。
冷凍室では詰め込みすぎても良い効果がありますが、冷蔵室は逆です。詰め込み過ぎはよくないんです。
冷蔵室に食品を詰め込み過ぎるデメリット

買い物をした後、買ったものをどんどん冷蔵室に詰め込んでしまうこと、ありませんか?
その時は充実感があるのに、後になって奥に隠れた食品が傷んでいたり、必要なものがすぐに取り出せなかったりするんですよね。
冷蔵室に食品を詰め込みすぎると、冷気がうまく回らなくなります。特に奥まで冷気が届かなくなり、冷えが悪くなってしまいます。
冷蔵庫が冷えないと感じた経験がある方もいるかもしれませんが、その原因は食品を詰め込みすぎて冷気の出口をふさいでしまっているからなんです。
さらに、見えないところに食品が埋もれると、同じ食品をまた買ってしまったり、賞味期限切れを発生させたりして、食品ロスにもつながります。私自身も、奥にあった牛乳が賞味期限切れになって、捨ててしまった経験がありました。ちょっとした見落としが、実は家計の無駄遣いにつながっているんですよね。
冷蔵室の中身を減らし、見通しを良くするだけで、無駄買いや食品ロスを防げる可能性が高まります。これが結果的に電気代にも良い影響を与えるのです。
では、実際にどのくらい電気代に差が生まれるのか、具体的な数字で確認してみましょう。
スカスカとパンパンの電気代比較
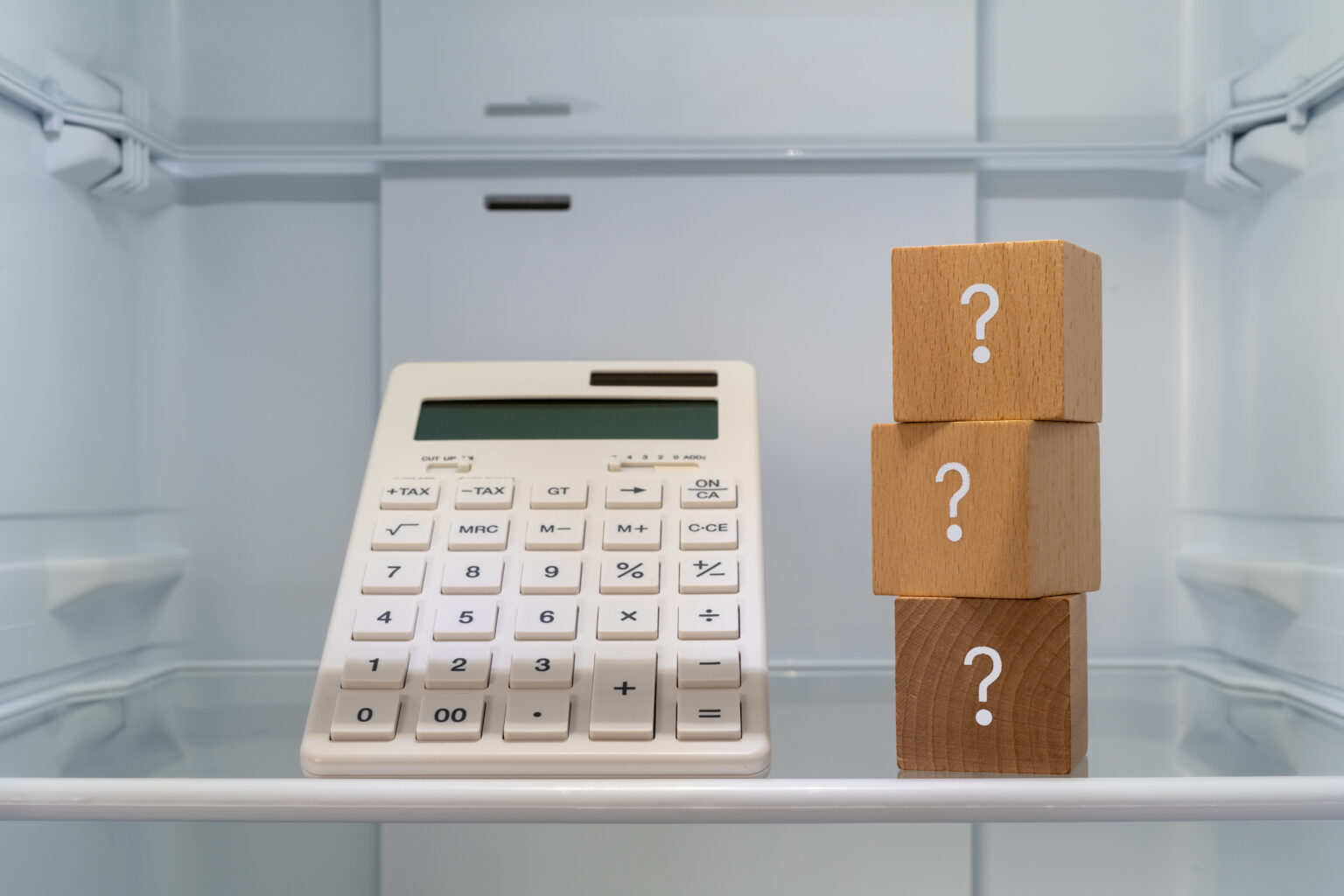
ここまで冷蔵室はスカスカが理想で、冷凍室はパンパンがベストだとお伝えしましたが、実際にどれくらい電気代に差が出るのか気になりますよね。
ここでは、スカスカとパンパンの場合、それぞれどれほど電気代に差が出るのかを、具体的な数値を交えて解説します。
1ヶ月あたりの差額は?
冷蔵庫の詰め方による電気代の差は、1ヶ月単位で見るとそれほど大きくないように感じるかもしれませんが、実は確実に差が生まれます。
一般的な家庭用の冷蔵庫(約400L)の場合、冷蔵室をスカスカにし、冷凍室をパンパンにした適切な使い方をしていると、月間の電気代はおよそ400〜500円ほど安くなることがあります。
逆に冷蔵室が食品でぎゅうぎゅうになっていると、冷気が庫内を循環しにくく、常に余分な電力を使い続けます。冷凍室も食品がスカスカの状態では、保冷効果が下がって余計な電力消費が増えてしまいます。
1ヶ月で数百円の差でも、毎日使う冷蔵庫だからこそ見逃せないポイントです。
年間ではこんなに節約できる
1ヶ月あたり数百円の差だとあまり実感が湧かないかもしれませんが、年間で考えるとその差は明確になります。
例えば、毎月400円の節約ができれば、年間で4,800円の節約です。月500円なら年間6,000円もお得になります。これはちょっとした家族での外食1回分にもなりますよね。
筆者自身、以前は冷蔵室に食品を詰め込みすぎていて、「冷蔵庫が冷えない」と感じていましたが、詰め方を意識してからは冷えがよくなり、年間の電気代も下がりました。小さな工夫で毎年これだけ節約できるなら、試さない手はありませんよね。
さらに電気代を下げるコツ

ここまでは、冷蔵室をスカスカにすること、冷凍室をパンパンにすることで節約できるとお伝えしました。ただ、冷蔵庫の電気代を下げるためには、他にも簡単にできるポイントがあります。毎日のちょっとした意識を変えるだけで、さらに節約効果が高まりますよ。
扉の開閉を少なくする
冷蔵庫を開ける回数が多いと、その度に庫内の冷気が逃げてしまいます。冷気が逃げると、再び冷やすために電気が多く必要になります。
実は、扉を1回開けるだけで、庫内の温度は約1〜2度も上がるといわれています。なるべく扉を開ける回数を減らして、まとめて食品を取り出すように心がけるだけで、電気代を抑えることができますよ。
筆者は以前、料理をするたびに何度も冷蔵庫を開け閉めしていましたが、料理を始める前に使う食材をまとめて取り出す習慣をつけたら、電気代が少し抑えられるようになりました。
設定温度を「中」にする
冷蔵庫の設定温度を低くするとよく冷えますが、その分電気を多く使います。逆に設定温度が高すぎると食品が傷む原因になってしまいますよね。
そのため、冷蔵庫の設定温度は「中」がベストです。「強」だと冷え過ぎて電気代が上がり、「弱」だと食品が傷みやすくなります。
電機メーカーの専門家も、「中」で食品の鮮度を保ちつつ、省エネできるよう設計しているとアドバイスしています。
温かい料理は冷まして入れる
できたての温かい料理をすぐ冷蔵庫に入れたくなりますが、これは節電の敵になります。
熱い料理を冷蔵庫に入れると、庫内の温度が一気に上がってしまいます。すると、温度を下げるために冷蔵庫は普段より多くの電気を消費します。
料理のプロによると、料理は常温程度に冷ましてから入れるのが良いそうです。熱いままだと料理の味も落ちてしまうことがあるので、節約だけでなく食品のおいしさのためにもおすすめです。
冷蔵庫まわりの整理を意識する
冷蔵庫周りにモノを置いている家庭は多いと思います。私も以前、冷蔵庫の上に調理家電や買い置きを置いていました。でも、それが実は電気代に影響を与えるなんて知りませんでした。
冷蔵庫の上や横にモノを置いてしまうと、冷蔵庫が放出する熱がうまく逃げません。冷蔵庫は熱をうまく放出できないと、その分、内部を冷やそうとして電気を余計に使ってしまうのです。
冷蔵庫の周囲は、両側と後ろ側に5~10cmの空間を空けるのが理想です。モノを置きたい気持ちは分かりますが、思い切って片付けるだけで毎月の電気代が減ることもありますよ。
買い替えタイミングを意識する
冷蔵庫は毎日使うため、長く使い続ける家庭も多いですよね。でも、実は冷蔵庫は古くなるほど電気の消費量が増えてしまいます。
特に、使用年数が10年以上の冷蔵庫の場合、最新モデルに比べて年間の電気代が数千円〜1万円程度高くなることもあります。
実際、私の知人も15年以上使った冷蔵庫を買い替えただけで、月の電気代が大きく下がって驚いていました。買い替えは出費に感じるかもしれませんが、長期的に考えれば結果的に節約になります。
まだ使えるからと我慢せず、節電効果を考えて買い替えを検討するのも賢い選択です。
今日から始める冷蔵庫の賢い使い方

冷蔵庫は毎日使う家電です。そのため、使い方をちょっと変えるだけで、年間の電気代を大きく抑えることができます。
大切なのは、冷蔵室はスカスカ、冷凍室はパンパンに保つこと。冷蔵室は食品の見やすさと取り出しやすさを重視し、冷凍室は隙間なく食品を詰めて温度を安定させましょう。
また、扉の開閉をできるだけ控え、冷蔵庫の温度設定は「中」に合わせます。温かい料理は冷ましてから入れ、冷蔵庫の周囲もスッキリと整理しましょう。
難しい節約法ではありません。日常のちょっとした習慣の積み重ねで、気づけば電気代も食品のムダも減らせます。ぜひ今日から始めてみてくださいね。











